    |
夜行バスで高知駅に着いたのが朝の7時半。夏休みも最終の日曜日だけあって早朝にも関わらず駅前は活気づいている。中心部のはりまや橋までは、路面電車とさでんもあるが、せっかくなので街をブラブラ見物しながら歩く方を選ぶ。実は、江戸時代から続く高知名物の日曜市が見たかったから。毎週、日曜日に高知城の追手筋で開催されている歴史のあるマーケット(朝市ではない)だ。そこでは高知で収穫された野菜や果物を始め、県の名産品が地元の人たちによって販売されており、8時前だというのに結構な人出で朝から活気に溢れている。そこで、冷やし飴という高知の飲み物を発見した。一杯150円。お湯で溶いた水飴を冷やして、最後にお好みで生姜を加える…甘いのにさっぱりしていて夏向きの飲み物だ。販売するおばちゃんから、「高知ではどこの家でも作って飲んでいる郷土の飲み物なんですよ」と教えてもらう。とても美味しかったと告げると満面の笑みでお礼を言われる。高知では「ありがとう」の語尾(とう)が上がる柔らかなイントネーションで、とても親しみを感じさせる。 高知城からUターンをして、追手筋と平行して走る高知の中心部・帯屋町にある“おびさんロード商店街”を歩く。隣に大きなアーケード商店街もあるが、ここは落ち着いた雰囲気が漂う石畳の通りで、小さなカフェやレストランが立ち並ぶ若者に人気のエリアだ。そのおびさんロードに、映画監督の安藤桃子さんが、2017年10月7日にミニシアター『Weekend Kinema M』を立ち上げた。安藤さんと高知県の出逢いは、2014年にオール高知ロケで製作された“0.5ミリ”に遡る。自身の介護体験を基に書かれた小説を映画化するにあたり、視察のため空港に降り立った瞬間に、「あ、この場所だ」と直感して高知に一目惚れ。ここをロケ地にする事を即決したどころか、撮影中、高知に住むことを決意する。周囲を気にして議論を戦わせようとしない…つまり人との摩擦を嫌う最近の風潮に疑問を抱いていた安藤監督は、マンパワーが強く思い描いた事がスピーディに進行する高知ならば、常日頃から主張し続けてきた愛の元に起きる摩擦による革命(これをピンク革命と呼ぶ)が出来る!と思ったのだ。孤独な老人たちの弱みにつけ入る押掛けヘルパーとなった主人公(安藤サクラ)が、逆に老人たちの心を癒して次なる高みへと導く姿を描いた“0.5ミリ”から漂う(どこかファンタジーのような)独特の世界観は、高知県が持つ風土や空気から生まれたのは間違いない。しかし、公開直前に想定外の事態が持ち上がった。高知での先行上映を予定していた“高知東映”が、閉館から10年が経ち老朽化による耐震構造の問題で断念せざるを得なくなったのだ。 |
   |
そこで閃いたのが高知城の真下に広がる城西公園に、仮設上映施設を作っての上映だった。公園を管理する高知市の共催と、“高知東映”からは劇場の椅子や備品などが提供された。そして、後に『Weekend Kinema M』設立に大きく関わる事になる建設会社の和建設が全面的にサポート。遂に、広さ450平方メートル、約170席の仮設映画館が出現すると、最初のひと月で約1万人を動員、2ヵ月のロングランが実現して大成功の内に幕を下ろした。この時、この仮設上映に心を動かされた人間がいた。当時、東京で映像関係の会社に務めていた宇賀朋未さんだ。「安藤監督が高知市内に仮設の映画館を建てて、自分の作った映画の先行上映をするって聞いて、同じ高知県人として居ても立ってもいられなくなったんです。気がつけば映画を観るため高知に戻っていました」と語る。「何かを手伝うという事でもなかったのですが、とにかく安藤監督に会って自分の思いを伝えたかったんです」何か大きなパワーに突き動かされた宇賀さんは、東京に戻ると早速、仕事を辞めたいと告げ、翌年夏には退社して高知に戻っていた。「だからと言ってすぐに何かを出来たわけでもなく(笑)しばらくは市内で移動上映をしている会社に就職して映写技術を磨いていました」その2年後…転機は突然訪れた。 仮設での上映以来、懇意にしていた和建設の社長から、おびさんロードにある解体予定の空きビルで何かやってみないか?と安藤さんは打診されたのだ。かつてここは東映・東宝・松竹と直営館が建ち並ぶ興行街。革命を実現させるならば映画館しかない!決断は早かった。早速、安藤さんは『Weekend Kinema M』設立に踏み出す。連絡を受けた宇賀さんは、迷う事無くスターティングメンバーとなった。支配人を託されると、そこから開設準備に取りかかり、僅か2ヵ月半という脅威の早さでオープンに漕ぎ着けた。「大変でしたけど一から作り上げていくのが楽しかった」と宇賀さんは当時を振り返る。 |
  |
解体予定の2018年12月まで1年ちょっと…期間限定のミニシアターだが、スタッフ全員パワー全開で挑んだ結果、オープニングには多くのファンが詰めかけた。こけら落としには“0.5ミリ”と“ザ・トライブ”、“20センチュリー・ウーマン”、そして、溝口健二監督特集(“山椒大夫”と“近松物語”は、フィルム映写機を持ち込んでのフィルム上映が実現)を上映した。本来、映画館が入ることを想定して作られた建物ではないため、消防法の関係からホールとロビーの間に仕切りの壁が作れず遮光カーテンで仕切っている。普段は外の音が漏れてくることはほぼ無いのだが、さすがに、よさこい祭り会期中は、祭りの音が入ってくるため、大音響での上映を開催するといった知恵で補った。お世辞にも広いとは言えないロビーだが、販売しているポップコーンは、高知のケンミンお菓子「あぜち食品」のものを提供していたり、チケット窓口も通りに面して設置したりと、映画館ならではのワクワク感が観る前から味わえる嬉しい作りになっている。 お客様の観る機会を増やしたいから、こちらでは通常より長い3週間切替で、毎回テーマに沿った名画・単館系・日本映画などを組み合わせて上映されている。そのテーマも男女や家族間などの「秘め事」だったり、海や青春など様々な「青」の形…と実にユニークだ。また、食のイベント土佐の豊穣祭の会期中にオオタヴィン監督の“いただきます みそをつくる子どもたち”を上映出来るのも地元の映画館ならでは。そんな60作品以上にも及ぶ名作を送り続けてきた中で、宇賀さんは思い出深い作品として、CINEMA FIGHTERS project<第二弾>の“ウタモノガタリ”で、安藤監督が手掛けたショートフィルム“アエイオウ”を挙げる。主演の白濱亜嵐によるレッドカーペットイベントには二千人近いファンが詰めかけたのだが…「この時、あの人出で事故が起こらなかったのが不思議と警備の人に言われました。でも、この成功は仲間の協力と参加されたお客様の意識の高さのおかげだと思うんです。これが高知の良さなんだな…と実感しましたね」 |
     |
  |
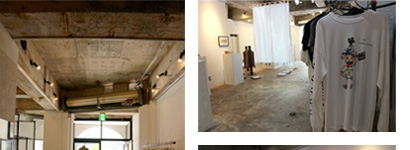   |
映画館の隣に12月26日にオープンした『& Gallery』は、「文化の土台として」をコンセプトとした多目的アートスペースだ。本質を表現するブランドとコラボレーションすることで、トップクリエイターによるモノづくりの土台になる事を目指している。中に入ると最初に目に飛び込んでくるのは、高知在住の鉄製家具職人・宇田津毅氏が製作したジャングルジムのオブジェ。奥行きのある簡素な色彩のフロア中央に薄い生成りの生地で間仕切りされている。これは、取材時に映画館で開催されていた特集との連動企画で、男女の秘め事をテーマとした小物やグッズなどを展示しているので、ここから先は15禁という意味だ(この演出も小洒落ている)。現在、月1のペースで国内外のデザイナーや職人がポップアップショップやインスタレーションを行ったり、時にはトークイベントやワークショップ、前述のような上映作品と連動した企画展なども開催されている。また、心地よい空間は音作づくりからはじまる…という事から音響にもこだわった。内田文昌堂のオーナーから、ウチで使っていたスピーカーで良ければあげるよ…と有難い言葉をいただき、そのまま受け継いだ劇場仕様の設備だ。こうして時には、心地よい音楽と高知の地酒や軽食も楽しめたり、アーティストを招いた様々なイベントも行われる大人の空間に変貌。老若男女がほんものを体験できる場所となっている。 今では映画ファンのみならず、多くのお客様に支持されるようになってきた『Weekend Kinema M』。高知県における文化発信基地のオピニオンリーダーとしての役割が明確になってきた。…とは言うものの、間もなく期限の12月が間近に控えているのも事実。このまま『Weekend Kinema M』は建物の解体と共に終わってしまうのだろうか?「オープンから1年…日を追うごとに、お客様が映画館を求めている事が伝わってきます。常設館の実現に向けて手応えも感じています。安藤もこのまま終わらせるつもりは無いはずですよ。次の企みを楽しみにしていてください」と和やかに応えてくれた宇賀さんの笑顔は力強い自信に満ち溢れていた。(2018年8月取材) |
【座席】 53席 【音響】SRD 【住所】高知県高知市帯屋町1丁目13-8アルカビル1F 【電話】088-824-8381
|