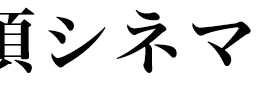|
|
大須商店街は、西を伏見通・北を若宮大通・南を大須通・東を南大津通に囲まれた愛知県最大の規模を誇る。その歴史は名古屋城が完成した慶長17年に遡る。出来た当初は城下町の南側に位置する神社仏閣の広大な敷地にあったため南寺町と呼ばれていたという。そこに移り住んだ人たちが、訪れる参拝者相手に商売を始めたのが大須商店街の始まりとされている。もっとも門前町として栄えたのは、名古屋城下の人口が増加したことで治安が悪くなったため、尾張藩が大須に住むよう奨励した頃から。その報奨として芝居や寄席などの興行を行う権利を与えたことで、多くの人が移り住むようになり賑わったのだ。大須が商店街より前に興行街・歓楽街として栄え発展した背景にはそんな行政の思惑があった。こうして芝居や寄席の見物客が集まることで周辺に飲食店が建ち並び、現在の大須商店街の礎を築いたのだ。 あまり知られていないが、実は大須は神戸や京都に並ぶ映画館発祥の地だ。明治30年2月に国内で二番目に映画の上映が、大須の若宮八幡宮境内にあった〝末広座〟で行なわれた。ちなみにキネトスコープと呼ばれていた映画が神戸で初披露されたのは前年の明治29年だった。そして明治41年に全国三番目の常設映画館である〝文明館〟が設立され、最盛期の昭和初期には23館もの映画館が軒を連ねた。戦争末期の名古屋空襲によって全ての映画館が消失してしまったが、それでも終戦の翌年から次々と映画館の再建が始まり、14館の映画館が新天地通を中心に復活した。名古屋全域が焼け野原となり失意の中にあった市民に、映画は夢と希望を与えて街の復興に大きく寄与した。昭和30年代にピークを迎えた大須の映画街も昭和34年にテレビが台頭したのを境に翳りを見せ始める。それでもまだテレビは庶民にとって高価だったため映画館に大きな影響はなかったが、昭和39年の東京オリンピックでテレビの価格が下がり一般家庭に普及すると、映画館は斜陽産業と囁かれ次第に大須から映画館が姿を消していったのである。最後まで残っていた成人映画館〝大須名画座〟が昭和63年に閉館したことで「映画館の街」と呼ばれていた大須から完全に映画館は姿を消してしまう。 |
それから30年間。映画館の無い街だった大須に映画の灯がともった。大須で衣料雑貨店を経営される中川健次郎氏と有志が「映画の街・大須を復活させたい」と、平成28年8月に市場の空きスペースを利用して自主上映会「大須赤門名画座」を開催したのだ。平成30年9月にはNPO法人『大須シネマ』を設立。常設映画館設立に動き出して、クラウドファンディングや賛助会員からの会費で約2,000万円の資金を集めた。かつての映画街・新天地通の近くにあった広さ約100平方の喫茶店だった場所に『大須シネマ』が完成したのは平成31年3月30日。場内はスタジアム形式の自由定員入替制で当日の朝から整理番号付のチケットを購入することが出来る。入口にはテイクアウトが出来る飲食ブースが併設されており、過去には〝世界の山ちゃん〟やフレンチトースト専門店が出店されていた(現在は休業中)。 プレオープンではこけら落としに〝禁じられた遊び〟と、活弁士を招いてロイドやチャップリンの無声映画のイベント上映を行なった。そして4月1日のオープンには石原裕次郎の名作〝嵐を呼ぶ男〟が上映された。当初は午前は名画、日中は若者向けのアニメ、夜はショートフィルムの三部構成となっていた。しかし令和2年に世界に蔓延した新型コロナウイルスによって緊急事態宣言が発令され『大須シネマ』も休館を余儀なくされた。設立から1年で閉館の危機に直面するが「大須に戻ってきた映画館の灯を消すのは忍びない」という思いから運営を現在の支配人犬飼堅太氏が代表を務めるデザイン会社「株式会社大丸」が引き継ぎ8月24日に再オープンする。再オープンのこけら落としは、〝きみの声をとどけたい〟〝南極料理人〟そしてフランシス・F・コッポラの名作〝タッカー〟の3作品。コロナ禍での再開だったため椅子を1席空けての観賞だったが、それでも再開を喜ぶ多くのファンが来場された。また〝タッカー〟の配給会社のご厚意でポスターが提供されて販売の収益は映画館への支援金となった。 |
 |
以降も映画ファンを唸らせる懐かしい名作がスクリーンを飾った。秀逸なのは特集の組み合わせ(思わず笑いを誘う特集のネーミングが秀逸)。ダリオ・アルジェント監督の鳥肌もののホラー特集やモノクロのホラー特集、そしてやけに登場率が高い(笑)サメ映画特集を繰り広げたり。かと思えば〝ハジメマシテ 日活ロマンポルノ特集〟では曜日によって男性限定デー・女性限定デーを設定するなどセンシティブな特集では配慮を見せる。夏休み期間はR指定の作品をやらずにファミリーで観られる特集をやった年があったかと思えば、中川信夫監督特集という渋い企画を持ってきたり…とただ映画を上映するのではなく、名画座ならではの実に心憎いプログラムを繰り出してくる。アート系アニメーション特集に〝緑子/MIDORIKO〟を持ってくる目利きは本物だ。上手いなぁと思ったのは季節に合わせた特集の組み方だ。例えば4月には「なんとなくソワソワ」と銘打って春の淡い恋心を描いた作品を特集したり、10月には戦争や芸術に翻弄された女性たちの〝テス〟と〝カミーユ・クローデル〟を組み合わせてみたり…このチョイスは朝からハシゴしたくなる。映画には特集の組み合せ次第で両方観たくなる化学変化が生まれるのだと思わせてくれた。「配給会社から提供される映画を順次上映していくのではなく、編成担当者を中心にスタッフの意見も取り入れながら独自に編成している」これは公式サイトでも紹介されていたが、ひとつの作品を選ぶにも未配信やディスク化されていない作品を探す手間ひまを掛けているからこそ、観客が予想もし得ない効果が生まれるのだと思う。新作と古い映画を組み合わせることで、午前の回を観たついでに「午後の映画は昔観た映画だけどまた観ようかな…」という気にさせてくれる。映画館がまるで本屋やレコード屋を訪れた時のように予定外の出会いがある場所になっているのだ。 |
|
映画館を再開した直後から『大須シネマ』は、まるでコロナで沈んだ社会の空気を吹き飛ばすかの如く、果敢に監督の舞台挨拶や様々なイベントを次々と繰り出していた。緊急事態宣言下でもオンラインの舞台挨拶を行うなど元気を与えてくれるスタッフ皆さんの努力には感謝しかない。特にセリフを抜いたアニメーション映画に声優が活弁士のように生アフレコをする「現代カツベン アニレコライブ」というイベント上映は映画館の新しい活用方法を提案する画期的なプロジェクトだ。声優の吹替パフォーマンスを生で観られるから「現代カツベン」というネーミングも最高ではないか。また昨年は若手クリエイターの登竜門〝大須インディペンデント・フィルム・フェスティバル〟を開催。300を超える作品が応募された。 是非注目していただきたいのがロビーに貼っているスタッフ手作りのポスターやポップだ。オリジナルのイラストやスタッフのコメント入りのポスターは目で楽しみながら映画を知ることが出来る優れものだ。やはり運営されているのがデザイン会社だからだろうか?とにかくロビーのあちこちに貼っている案内のポップにセンスの良さが光るのだ。ミュージカル映画特集では作品のイメージに合わせてロビーの天井を風船でデコレーションされたり、SF特集の時はロビー全面を銀紙で覆ってしまったのだ(これは感動!)。ブログには完成までの制作風景が写真付きで紹介されているので是非見ていただきたい。ここからスタッフが楽しまれているのがよく伝わってくる。 長いロビーの先にあるスペースには映画関連書籍やパンフレット、ガラスケースには様々なチャッキー人形が展示されている。ロビー活用の一環で、書籍や中古パンフレットは販売もされている。そこで棚にあった本の一番上に私が出版した「日本懐かし映画館大全」が置かれているのを見つけた。これはスタッフの皆さんが私が取材に来るというのでお気遣い頂いたのだろう。嬉しい反面照れ臭さを感じつつ、受付にいらしたスタッフの皆さんに感謝の意を述べさせていただいた。ちなみにロビーでは不定期ながら色々な展示会も行われている。例えば古着をリビルドしたファブリックボードの展示販売を行ったり、手作り体験ができるワークショップを開催するなどユニークな企画が行われている。ちなみに今回の記事はネタ元の多くを公式ブログから参考にさせていただいているが、定期的に更新されているブログの情報はとても充実して読み応えがある。上映された作品やイベント情報は勿論だが、たまに大須商店街にあるオススメのお店などの情報も載っているので映画館に行く時は、予めチェックして出掛けられると良いだろう。映画だけ観てそのまま帰ってしまうなんて『大須シネマ』に限っては実に勿体無い話なのだ。(2024年11月取材) |
【座席】42席 【住所】愛知県名古屋市中区大須三丁目27番12号 【電話】052-253-5815
|