
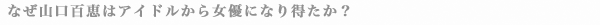
山口百恵が『伊豆の踊子』で映画初主演を果たした昭和四十九年の日本映画界は入場者数が下降をたどり続け混迷を極めていた時代だ。ヒット作が生まれず手の打ちようが無くなった大手映画会社は撮影所の土地の切り売りを始める。昭和四十六年に大映が倒産し、同じく経営不振に陥っていた日活は経営方針をロマンポルノ路線に転換。実は山口百恵の女優として成功した背景にはこの二大映画会社が大きく関わっているのだ。『伊豆の踊子』を監督した西河克己や撮影の萩原憲治ら殆どのスタッフは元日活のメンバーで構成され、撮影所も日活スタジオが使われていた。最初は気にならなかったが改めて観ると東宝色よりも日活色が強かったのだなぁと気づく(純東宝製ならばもっとトーンが明るくなっていたはず)。東宝の砧撮影所を使わなかったのはホリ企画(ホリプロの企画会社)の笹井英男プロデューサーが元日活社員で経済性と気ごころを知っているから…という理由に因る。そしてもうひとつ、彼女がテレビドラマで確固たる地位を築いた“赤い疑惑”を代表する赤いシリーズの製作を行ったのは言わずもがな大映テレビ…つまり大映が倒産直前に分社化して存続させた製作会社だという事。皮肉にもテレビの台頭によって経営を圧迫された映画会社がテレビから誕生したアイドル山口百恵を女優へと成長させる一役を担ったという事になる。ある意味、女優・山口百恵はこの時代に生まれるべく運命にあったのかも知れない。

ちなみに山口百恵の主演作13本のうち8本がリメイクものである。(そのうち5本が日活作品というのも興味深い)当初、デビュー作についてホリプロ側は学園ドラマを…と要望していたというが西河監督がこれに異を唱えた。そこで東宝が代案として提示してきたのが『伊豆の踊子』である。(詳細は下段キーワードにて)このような画策があったとは言え本作における彼女は最高だった。三浦友和演じる書生への憧れを体いっぱいに体現して、あれこれと世話を焼く姿から見える純真な乙女ごころに何度も目頭が熱く(泣かせる場面でもないのに)なった。結果は予想外の大ヒットを記録。そこで山口百恵主演による文芸名作のリメイクを製作する事が決定したわけだ。続く『潮騒』と『絶唱』では前作のような受け身の演技ではなく、もう少し高度な演技が要求されるも各段に上達したセリフ回しや表情を見せる彼女に驚く。続く『エデンの海』は彼女自身「不完全燃焼だった」と語るように昭和三十八年の現代劇をそのまま昭和五十一年に持ってきたのには無理があり、主人公・清水巴の奔放さがセンセーショナルではなくなってしまった。その失敗を踏まえてまた文芸作品に戻ったのが『風立ちぬ』である。清楚なお嬢様という出で立ちはピッタリのイメージだったが、難病ものは当時ヒットしていた“赤い疑惑”と被るところがあり、映画としてはテレビの延長線に見られたのは仕方ない。しかし、6作目にして初めてのリメイクではない作品…谷崎潤一郎の『春琴抄』で、ひと皮剥けた山口百恵に出会う事となる。明治初期、大阪の薬問屋に生まれ(関西弁が新鮮だった)幼い頃に失明して周囲から気を使われて育った事でエゴの固まり暴君と化した春琴のわがままぶりは素晴らしかった。何よりも特筆すべきは、本作が三浦友和の映画である事。奉公人という身分をわきまえ下僕の如く春琴に尽くす佐吉を見事に演じきっていた。春琴の冷えた足を佐吉が懐に入れて暖めるシーンのエロティシズム溢れる美しさには今でも鳥肌が立つ。
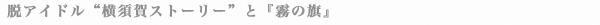
『泥だらけの純情』と『霧の旗』で再び現代劇のリメイクものに挑むが、松本清張のミステリー『霧の旗』では無実の兄を見捨てた格差社会に対してホステスに身を宿し復讐するという初の汚れ役に挑戦。三国連太郎を相手に身体を使って誘惑し、遂には破滅させてしまう…というハードな役を十八歳にして見事にこなしていた。西河監督は「『伊豆の踊子』の美しさは百恵の素顔の美しさ。『霧の旗』の美しさは女優の美しさである」と述べていたのは言い得て妙だ。彼女は前年に“横須賀ストーリー”を発表しており、それまでの清楚なイメージから一転して、内なる魔性性を既に解放していた。この頃の山口百恵は芝居にしても歌にしても“自分のイメージ”というものを敢えて破壊しようとしているように思われる。『霧の旗』も“横須賀ストーリー”も自ら切望して実現した企画だ。当時のインタビューで「自分の芝居に対してこうだというものが無い」と語り、手探り状態で今までの自分に無いものに挑む…「いずれは、これだと思うものを掴みたい」という彼女にとって固定化されたイメージは邪魔な足枷だったのだろう。そんな彼女にとってまた転機が訪れる。『霧の旗』を最後にしばらくはリメイクものからオリジナルの現代劇が続くのだが仕掛け人は大林宣彦。『ふりむけば愛』の監督も務めた大林はプロデューサーとして作家性に富んだ監督と組ませて今までにない新しい山口百恵を引き出そうとした。『炎の舞』『ホワイトラブ』と今から思えば様々な実験をしていた事がよく判る。彼女自身も意欲的にステレオタイプ的なイメージから脱却しようと挑戦を続けていたのだろう。観客はそんな山口百恵像に戸惑っていたようだった。しかし、その試み(山口百恵というコンテンツを媒介に…)は実に楽しいものだったし、そのおかげで以降彼女の演技が多様化してユニークな一面を見れるようになったのも事実だ。藤田敏八監督の『天使を誘惑』では生々しい等身大の山口百恵を披露…そこにはアイドルの片鱗を見る事は出来ない。同棲、妊娠、中絶そして結婚…このラストシーンの先に待ち受けている主人公たちの未来を想像すると決してハッピーエンドとは言い難い。いよいよ女優としての新境地に足を踏み出したこの翌年、彼女は三浦友和との婚約を発表と同時に引退を宣言する。引退直前に和田勉が彼女の引退番組で対談した時のエピソード。和田が「たった二十歳で引退するとは何ですか?」というちょっとキツメの(これは和田の作戦)質問に対しての返答が実に彼女らしい…本心からの明確な内容だったのが印象に残る。「私は常に命じられた通りにやりました。これ以上続けると私は“正確な機械”になるのではないか、と思って…自分の“正確さ”に飽きたのです」彼女はそれまでの芸能生活を正確という言葉で総括していたが、自分本来の考えや意志を作品に投影出来るのは二十代後半や三十代だったかも。同番組内で父親との確執にも言及していたが、彼女の引退映画『古都』で、自分が捨て子だった事を独白する場面でそっと手を差し伸べようとした幼なじみに「捨て子に触らんといて…」というセリフがある。彼女の(実生活における)父親に対する思いをもうひとつ踏み込んで演技に取り入れる年齢になれば表現が変わっていたかも知れない。
引退後、潔いほどにメディアの前から姿を消した山口百恵。コンサートでは決してアンコールに応えずステージに戻らなかった彼女の姿勢とダブる。それは『古都』のラストカットにも現れていた。双子を演じた彼女が「また来ておくれやす」と言う姉の言葉に何も言わず首を横に振り朝靄の中に消えてゆく妹の姿は個人の「山口百恵」が芸能人の「山口百恵」と訣別しているようではないか。
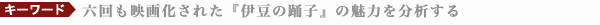
西河克己監督がまとめあげた「伊豆の踊子物語」(フィルムアート社刊)は大変興味深く読む事が出来る優れた研究文献だった。小説「伊豆の踊子」の成り立ちから、映画『伊豆の踊子』六作品の世界観、さらには服装や立札、別れの場面の贈り物などの扱い方を細かく比較しているのが楽しめる。西河監督自身、昭和三十六年に吉永小百合主演版(日活)と昭和四十九年に山口百恵主演版(東宝)を手掛けており、原作と映画を客観的に比較分析する。(自身の作品に関してはワイズ出版刊・権藤晋共著による「西河克己映画修業」から引用するという徹底ぶり)今回、全作品を観返そうと押入の奥からDVD未発売三作品の埃を被っていたビデオを引っ張り出して改めて観ると時代や監督の意図によってポイントの当て方が結構大胆に異なっているのが発見できて面白かった。
まずは原作が発表されて八年後の昭和八年に松竹で製作された五所平之助監督、田中絹代主演による記念すべき第一作目『恋の花咲く・伊豆の踊子』(サイレント版)が原作と設定が大きく変わっている事に驚く。主人公の栄吉・薫の兄弟は温泉旅館の跡取りだったが、栄吉の放蕩三昧で旅館は人手に渡り、今では旅芸人に身をやつした…という伏見晃による大胆な脚色が施されているのだ。そこに利権を巡り兄弟を利用して金儲けを企む悪党が出てきたり中盤は栄吉の復習劇の様相を呈するなど…原作を知る者はかなり戸惑ったのではなかろうか?これは原作が映画的に地味な内容だったため、松竹蒲田が得意とするメロドラマ調に仕立て、いくつもの山場を作らなければ当時の観客には受け入れられなかったからであろう。(西河監督曰わく、当時の映画界では珍しくなかったそうだ)川端康成は本作を観た後、「私が映画を平気な顔で楽しく見てゐられるのは、映画が原作を非常に離れてゐたからである」と述べていたのが印象的だった。それにしても田中絹代の薫は実に可憐で良かった。全作品中で最年長の二十三歳であるにも関わらず子供っぽい愛くるしさ(行儀悪くうどんを食べる演技は今観てもビックリする)は最も薫のイメージに近かった。なかでも冒頭の登場場面で一瞬だけ見せる草むらで用を足していたとおぼしき薫のはにかむ表情は逸品だ。続く昭和二十九年に作られた野村芳太郎監督による二作目はてっきり美空ひばりが主演だから音楽映画になっているものだと思いきやあえて歌を封印(歌う場面はあるのだがお囃子程度)、これが正解だった。当時のひばりは既に国民的スターだったわけで、歌うと彼女のカラーが強く出過ぎると判断したのだろう。内容は前作とほぼ同様だが旅のルートは沼津から西伊豆の海岸線を通って中伊豆に入る…となっているため駿河湾の彼方に富士山が見える画が珍しかった。その六年後の昭和三十五年、川頭義郎監督、鰐渕晴子主演の三作目は六作中もっとも異色な印象を受けた。それは間違いなくドイツ人の母を持つ鰐渕のエキゾチックな顔立ちに由来しており、薫の性格も自己主張をハッキリとする現代風の少女となっていた。そしてもうひとつ、前二作と異なるのは旅芸人としての生き様のようなものを描いている点である。酔客に絡まれた薫を守るために酒を飲み酩酊しながらも一人で店を渡り歩く四十女(たつ)の姿にカタルシスを感じた。書生と別れた薫が百合子とたつの女三人で旅を続けるラストも女芸人の悲哀と力強さを表現した素晴らしい場面となっていた。作品としては良いのだが原作のイメージから一番遠い作品となった印象は否めない。
それまでは松竹大船で製作されていたが昭和三十八年の西河克己監督、吉永小百合主演による四作目は日活で作られている。『青い山脈』などを手掛けた西河監督だけに前三作のようなメロドラマではなく爽やかな青春映画の要素が強く、書生と踊子の間に流れる感情は恋愛というより踊子の憧れ…といった描き方をしている。これは脚本家の井手俊郎がドラマチックな要素や原作にいない人物を創作せず、オリジナルに近づこうという姿勢の表れであった。しかし、現代の場面が入るプロローグとエピローグについては賛否両論の物議を醸しだし、無くても良かったという意見が大多数を占めた。また吉永の聡明な顔立ちから育ちの良さが漂い、十六歳の無垢な踊子のイメージから離れていたのが残念だ。(サユリストの川端康成は喜んでいたそうだが…)むしろ七年後に作られた恩地日出夫監督による五作目(ここから東宝が続く)で踊子を演じた内藤洋子は身近にいそうな女の子…という健康的な可愛らしさを兼ね備えており良かったと思う。峠で休憩している書生をじっと見つめる表情(恥じらいの無さ…とでも言おうか)は現代的だ。そして、昭和四十九年に作られた西河克己監督の二度目となる山口百恵のデビュー作は何と言ってもラストのストップモーションの衝撃に集約される。恵まれた環境にいる書生と対照的に酔っ払いに絡まれる踊子。彼女はこれからも同じような日々を繰り返すであろうと暗示する胸を締め付けるエンディングだ。百恵自身、感想を聞かれた時「ラストの場面がストップモーションになってドキッとしました。これは映画なんだ、と思いました」とコメントしていたが、正にこのラストは半世紀近く映画化されてきた『伊豆の踊子』の結論と言っても良いかも知れない。
「伊豆の踊子」は45ページの短編であるから映像化するにあたり創作部分を膨らませる事が出来る…というのも映画化が多い要因かと思われる。しかも、踊子の薫に関して言えば具体的な容姿の記述は極めて少ない事から新人女優を自由に起用しやすいキャラクターであるのも確かだ。百恵版を最後に四十年近く映画化されていないが是非、平成生まれの女優がどんな薫を演じるのか見たいものだ。

山口 百恵(やまぐち ももえ 本名:三浦 百惠 1959年1月17日 - )MOMOE YAMAGUCHI
東京都渋谷区出身。
幼少期を神奈川県横須賀市で過ごし、1972年12月、オーディション番組スター誕生!で、準優勝。1973年4月、映画『としごろ』に出演と同時に同名の曲で歌手としてデビュー。森昌子・桜田淳子と共に「花の中三トリオ」と呼ばれる。1974年日出女子学園高校に入学してから間もなく発売された“ひと夏の経験”が45万枚を売り上げて“青い性”路線を開花。また、カメラマン篠山紀信による「激写」のモデルが爆発的ブームを呼び、デビューから二年目にして人気は急上昇を続け、この年にNHK紅白歌合戦の初出場を果たす。また同年秋よりTBS系の“赤い迷路”がスタートして、以後“赤い疑惑”“赤い運命”等のシリーズで運命に翻弄されるヒロインを好演。赤いシリーズは30%の高視聴率を稼ぐドラマへと成長していった。更にこの年正月作品として公開された映画初主演作品『伊豆の踊子』が大ヒットを記録。以降、山口百恵主演作は東宝のドル箱となり、13本もの作品が製作された。この映画で共演した三浦友和とはゴールデンコンビとして『エデンの海』を除く作品が百恵・友和映画というジャンルで人気を博した。ブロマイドの年間売上成績で第1位に輝いた1976年には阿木燿子と宇崎竜童による“横須賀ストーリー”と“イミテーション・ゴールド”そして“プレイバックPart2”で、それまでのアイドル歌手のイメージを一新。同様に映画でも『春琴抄』や『霧の旗』といった新しい役柄に挑戦する。1979年10月20日のコンサートで三浦友和との交際を宣言し、その半年後に婚約発表と引退を発表。1980年の正月作品として公開された『古都』が最後の主演作となり、一人二役の双児は8年の女優人生を締めくくる最高の演技を披露する。
 |
 |
【参考文献】
女優 山口百恵
203頁 20.8x14.8cm ワイズ出版
四方田犬彦【著】
|
 |
 |
【参考文献】
伊豆の踊子物語
238頁 20.8x14.8cm フィルムアート社
西河克己【著】
|
 |
 |
【参考文献】
蒼い時
261頁 19.4x14cm 集英社
山口百恵【著】
|



