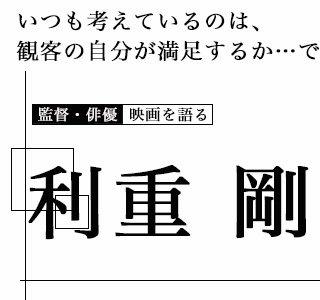|
九州のとある田舎町。人気の無い道を走る朝の巡回バスは通勤客もまばらだ。そこへ一人の男が乗り込んで来る。ガラガラの車内。席に座るわけでもなく吊り革に身体を委ね外の景色を眺めている…どこにでもありそうな日常の風景と、どこにでもいそうな普通の人々。男を乗せたバスは終着地の駅へと静かに走り出す。やがて観客はその穏やかな光景が狂気の序章であったことを思い知らされ愕然とする。そして、駅の駐車場に止まるバスから走り出す乗客を男は背後から撃ち殺す場面が続く。何が起きたのか?何が起こっているのか?理解する事も出来ずに震える乗客を気にも留めず、男は飄々と持っている拳銃で殺戮を繰り返す。男を演じるのは利重剛。映画は、青山真治監督作品『EURIKA ユリイカ』の冒頭シーンだ。まるでスーパーで食材を選ぶような表情で乗客に銃口を向ける男の怖さ。史上最悪のバスジャック事件によって人生を狂わされてしまった生き残った人質のその後を描く本作にとって、強烈なインパクトを与える必要があったバスジャック犯の異常性を見事に体現してみせた利重剛こそ、本作を成功へと導いたキーパーソンであったのは間違いない。普通に世間話をしながら人を殺せる犯人の姿に、いつかテレビで見たデビュー作『父母の誤算』の高井洋二を思い出していた。その時に感じたのは、見た目では分からない内に秘めた静かな狂気だった。共演していた直江喜一は既に『3年B組金八先生PART2』の加藤優役で知られていたが、初めて名前を聞く俳優の演技を前に、しばらく画面から目が離す事が出来なかった。これが俳優・利重剛との出会いだった。
それから間もなく…利重剛の姿はスクリーンの中にあった。映画は岡本喜八監督の『近頃なぜかチャールストン』。錚々たるベテラン俳優陣を抑えてトップバッターにクレジットされていたのだが、実は本当に驚いたのは、脚本に利重剛の名前が映し出された時だった。「僕が成蹊高校3年の時に映画研究部(先輩に手塚真監督がいる)で撮った8ミリ映画『教訓1』を“ぴあフィルムフェスティバル”に出して、池袋の文芸坐で上映される事になって、その時、岡本監督に手紙を送ったんです。それもかなり分厚い…(笑)僕がどれだけ岡本監督の映画が好きかとか、今度、僕の作った映画が文芸坐で上映されるので良かったら観に来て下さいませんか…という内容を延々綴っていました。そしたら本当に観に来てくれたんですよ。その後に監督から電話も掛かってきて、もうビックリしちゃって。一度遊びにおいでって言ってくれたので、ご自宅に遊びに行ったんです」その頃は既に『父母の誤算』で俳優デビューして注目を集めていた時だった。岡本監督から「君は監督になりたいの?それとも役者をやりたいの?」と聞かれると、「自分はまだ何も考えていなくて、色々な現場を見たいから役者を始めたけど、今はまだ分からないです」と答えたという。既に日本映画界はスタジオシステムが崩れており、助監督で叩き上げて来た者よりも、これからは有名な人が映画を撮る時代が来ると確信していた岡本監督は、役者を続けて行く事と、とにかく脚本(ほん)を書けるように…というアドバイスをされた。「これからは脚本を書ける人じゃないと監督になれない。自分で脚本を書いて、こういうのを撮りたいんだけど…と言える人間が監督になれる時代が来ると言われました」そしてプロの現場を覚えるために助監督を数本経験する事を薦めた岡本監督は、これを一緒にやらない?と、『近頃なぜかチャールストン』の原案を持って来て、その場で助監督と脚本と出演が決定してしまった。 高校の中に徴兵制が起きたら…という話しの『教訓1』と、平和ボケした戦後の日本で老人たちが一軒家を占拠して独立国家を作ってしまう話の『近頃なぜかチャールストン』は、根底に流れているテーマに類似点がいくつもあった。岡本監督が「君の映画を観た事で、それまで悩んでいたプロットが進み始めた。だから、君はこの家に来る前からこの映画に参加しているようなものなんだよ」と言ってくれた事を今でも忘れられないと語る。「岡本監督から、君の映画を観たら、まぁデタラメで面白かった。俺は東宝という色々な監督がいる会社の中で、どれだけデタラメに自由に野方図に撮れるかが、自分の持ち味だと思っていたけど、自分もいつの間にか丸くなっていたのかな?と君の映画を観て思ったよ…って。僕は慌てて否定しましたよ(笑)だって、ワザとデタラメにやってるんじゃなくて、作り方が分からなくて結果、デタラメになっているんですからね。そうしたら岡本監督は、俺が観て面白かったんだから全然関係ない。映画は面白い事が大事なんだと言ってくれたんです」今では俳優だけではなく監督・脚本から若手クリエイターを支援するなどマルチな活躍をされている利重剛に、多大な影響を与えたのは岡本喜八監督である事に間違いなさそうだ。「とにかく、岡本監督が好きでした。既に東宝の巨匠なのに自分の家を抵当に入れて映画を作ったり…僕にとっては、インディペンデント映画の神様みたいな人ですよ。全ては岡本監督から教わったと思っています」
「でも…その当時はまだ、俳優で行こうとか監督で行こうとか決めていなかったんです」既に『近頃なぜかチャールストン』から5年…21歳の時に『見えない』という自主映画を撮っただけで、4年間映画は作っていなかった。「25歳まで鬱々としていたんです。若い時ですから色んな事でグルグルしちゃうんですよ…色々と悩んじゃってしばらく休んでいたんです」勿論、その間にも俳優としての活動は続けていた。残念ながら日本では公開されなかったポール・シュレイダー監督の傑作『MISHIMA』で、若き日の三島由紀夫を演じていた。(ちなみに、輸入版のVHSを昔に購入して観る事が出来たが素晴らしい作品だった)「もし、それが公開されていたら何か大きく変わるだろうと思っていました。でも結局、日本未公開となって…どうやって生きていこうか等と色々思っていたんです。そんな時期にある番組で大島渚監督とお会いしたんです。ちょうど監督が『戦場のメリークリスマス』撮影直前の頃で、本当は僕を連れてって下さいと頼むつもりでいたんですけど、大島監督から25歳だったらそろそろ本編を撮る頃だね!って言われたんです。20代後半に頑張っていたら、この後いくつになっても頑張れるから今が大事な時だね…って。その時、そうか!俺は今頑張らなくちゃいけないんだって思ったんです。そして、その後家にこもって書き上げたのが『ザジ ZAZIE』なんですよ」 だからと言って順風満帆に制作会社が決まったワケではなかった。当初、想定していた映画会社から断られてしまい、自分の足で色々な映画会社を回っていたのだ。「そこで出会ったのが、アミューズだったんです」当時、プロアマ問わず若い才能に10本の映画制作を支援していたアミューズに脚本を送ったところ、社長から会長の手へ渡り…「お前、どうしてもこれを撮りたいんだろう?じゃあ撮ればいいじゃないかって(笑)しかも主役を演じた中村義人を、長崎で良いバンドを見つけたんだって紹介してくれたんですよ」イッキに話がトントン拍子に進んだ背景には、アミューズ会長の即断があったおかげだが、その理由を聞いてナルホド…と納得してしまった。「どうしてお前にこれを撮らせるか分かるか?って会長に聞かれたんです。会長は映画が好きだから、この企画を打ち上げたんだけど、応募して来た人たちは、皆、誰かの紹介だったり、企画書もペラ2枚程度の代物…どうやら脚本を最後まで書き上げてノコノコやって来たのは僕だけみたいなんです。だから撮らせてやるんだ…って(笑)。その時、思ったのは、信じる馬鹿が勝つっていう事でした。そこでも実績が評価されたわけでもなく、ただやるべき事をやったらそうなった…っていう感じでした」 かくして利重監督の長編一作目となる『ザジ ZAZIE』が1989年10月14日に公開された。カメラマン井出情児のクールな映像と、ザジが彼を取り巻く女性たちと交す会話の端々に、思わずカッコイイ!と唸ってしまった。突然、人気絶頂の中で表舞台から姿を消したザジが再び街に戻ってくる…彼が戻った事で周囲の者たちは浮き足立つ。本人が変わろうとしても周囲が変わろうとせず、むしろその変化に対して憎悪を抱く者も現れる。それは、3作目の『BeLrin』にも通じるものがある。中谷美紀扮する人気の風俗嬢のキョーコがある日忽然と姿を消す…ドキュメンタリーを撮っているクルーたちや仲間のホテトル嬢たちの会話の中から、おぼろげながら見え隠れするキョーコの残像…両作品共に一人の人間を軸とした群像劇というのがユニークだ。特に強いわけでもなく、現実の世界に違和感を感じる二人の主人公たちの姿に、岡本喜八監督の『肉弾』や『ああ爆弾』の主人公たちがダブったのは、筆者だけだろうか。続いて高校時代からボリス・ヴィアンのファンだった利重監督が、小説“日々の泡”と“うたかたの日々”をモチーフにした『クロエ』を手掛ける。「これは念願の企画でしたからね…実際にやってみたら原作のモチーフだけ借りて全然違うものになってるので何とも言いづらいんですけど(笑)」本作の前年に、前述した『EURIKA ユリイカ』で衝撃的な演技を見せただけに、同一人物が、こんなにも優しく美しい映画を作れるものなのか…と、驚いた記憶がある。 5作目となる『さよならドビュッシー』は、利重作品には珍しく、既に進行していた企画もので、中山七里原作の音楽ミステリーの映画化だった。引き受ける条件として脚本を全て書き直させてもらった(ここが利重監督らしい!)というが、その時、岡本監督から言われた事を思いながら脚本を書いていたそうだ。「原作でも脚本でも最後まで読んで一行でもピンと来るところがあったら、その一行を元に書いてみなさい。そこに自分が描きたいものがあるはずだから。監督というのは映画を面白くする事を考える人なんだよ…という言葉を考えながら書いていました」音楽を劇中に取り入れる事に関しては右に出るものがいなかった岡本喜八監督。『ジャズ大名』の製作時には楽譜に絵コンテを描いていた事を利重監督は懐かしそうに話してくれた。「音楽コンクールが最大の見せ場なんだから、最後の2曲はフルで聴かせて、そこを中心にやろうと思ったんです。岡本監督がフィルムの時代に『血と砂』や『ジャズ大名』を作れたのに、今の時代に撮れないはずがない!って…だから僕も楽譜に全部コンテを描いて撮影に臨んだんです」利重監督が、そういった意味において、この映画は全て岡本喜八監督へのオマージュだという。「僕は自分で勝手に岡本監督の最後の弟子と思っているにも関わらず、岡本喜八タッチの映画を全然作った事がなかった。だから僕だって、ちゃんとエンタテインメントを作れますっていう表明のつもりだったんです。(依頼された企画でも)その中に自分のメッセージを一言でも入れられるか…?それを前面に出すのではなく、スッと忍び込ませる事が大事なんだと常々言ってたのは、その通りだなぁと思いました。だから、これは好きな映画なんです」 「結局は自分が観たい映画の脚本を書いているんです」と語る利重監督。それは、一歩引いて、観客としての自分を信じている…という事だ。「ずっと映画が好きで観続けて来た僕が好きな映画は良い映画だろうと(笑)。映画を作る前の僕は、“観たい!”と思える映画を誰か作ってくれないかな…と思っていたのですが、誰も作ってくれないから自分で作る事にしっちゃったんです」そう、利重監督が映画を作ろうと思った根っこの部分は、映画を楽しむ観客の立場から始まっているのだ。「そりゃあ、観客が一番いいもんね。映画を観て、面白かったな〜とか、ツマんなかったな〜って、誰かと語り合うのが一番楽しいんですよ。だからずっと観客でいられるならこんな幸せな事は無いのですが…ある時から自分が観たいと思える映画が少なくなって来たんです。だったら自分で映画を作ってみようと。だから、監督になった今でも考えているのは、観客としての自分が満足するかどうかという事です」利重監督は評論家の採点表や賞の事は全く意識していない。あくまでも映画作りの先にあるのは観客にどう感じてもられるか…という事だけだ。「勿論、全てのお客さんに気に入ってもらう必要は無くて…10人いたらそのうちの2〜3人でもいいんです。いや、たった1人でも、この映画の凄さを分かっているのは俺だけだ!って思ってくれたら嬉しいですよ。もしかすると僕だって分かってないかも知れない。もうそれは監督を飛び越えて、お客さんが100人いたら同じ映画から100本の映画が出来上がるようなものです」つまり映画館に映画が掛かった時点で、その映画は監督のものではなく観客のものになってしまう事だ。「映画って監督が作るんじゃんじゃなくて、お客さんが観て初めて出来上がるんです。それくらい想像力があるんですよお客さんって…。だからイイんです」そして観客の頭の中に、想像力を膨らませるためのササクレをどれだけ映画の中に入れられるか…が監督の力であると付け加えた。 |
|
|
Produced by funano mameo , Illusted by yamaguchi ai
copylight:(c)2006nihoneiga-gekijou |