2011年秋、ある家族の記録を収めたドキュメンタリーに出会った。その映画の主人公は定年退職して間もない砂田知昭氏(69歳)。そして監督は知昭氏の次女・砂田麻美。熱血仕事人間だった父親に興味を持ち、会社が開催する定年退職パーティーにまで同行してカメラを向けていた砂田監督の前に突きつけられた父親の癌宣告。知昭氏は人生の最後を迎えるにあたって“エンディングノート”という死後の段取りを綴ったマニュアルを書き始める。以前から習慣的に家族の日常をビデオカメラで記録していた砂田監督も一時はカメラを置いて撮る事をやめるが再びカメラを手にして完成させたのが『エンディングノート』だ。この映画はひとりの男と、その家族が迎える“最後の日”までを綴った物語だ。最近では珍しくなった50代から70代とおぼしき年輩のご夫婦が連れ添っている満席の場内。映画の後半ではアチコチから鼻を啜る音が聞こえ、場内が明るくなるとご主人のほうがハンカチで目頭を押さえてる姿が目立つ。娘として監督としてこの映画に真正面から向き合ってきた砂田監督に、改めて現在の率直な思いを聞いてみた。

カメラを回していた時は映画にしようとは全く考えていなかったという砂田監督。以前から日本の典型的なサラリーマンであった父の姿に興味を持ち、機会があればカメラを回していた(映画の中でも撮り溜めていた映像がいくつも紹介されている)という。「父の病気が分かった頃はむしろカメラを回す気が全然起きなくて、目の前に起こった現実に対応していくのが精一杯で…」と当時を振り返る砂田監督が知昭氏や家族にカメラを向け始めたのは治療が始まり気持ちが少し落ち着いてきた頃だ。「まずは日常の一部を記録する感覚で撮っていたんです。孫が遊びにきたのでカメラを回すというのはどこの家庭でもあると思うのですが、それと同じなんです」家族としての父親を記録しておきたかったと語る砂田監督は「子供の運動会で親がビデオを回すのは、その時の子供の姿は確実に消えて無くなるから少しでも多く残しておきたいから。父にカメラを向けたのは、その気持ちに似ています」と例える。家族の団欒や思い出を記録として残すという以前と変わらぬ気持ちで撮影していた砂田監督だったが時間の経過と共に、ある変化が現れてきたという。「日常の延長線上で撮影を始めましたが、父の病状が悪くなってくると私の撮り方も変わってきたのです。どうしても映像を職業にしているせいでしょうか…ある日、カメラを持つとディレクター的な視点になっている自分がいたんですよね」撮影をしている内に砂田監督は娘としてではなく取材者として、こういう表情を捉えたいとか、こんな場所にもついて行きたい、こういう言葉が引き出せたらイイな…という欲が出ている事に気づく。「そんな気持ちで父にカメラを向けるのは残酷すぎると思ったんです」そこまで語ると砂田監督はちょっとだけ間をおいてこう続けた。「それって健全な親子関係じゃないですよね」そこで砂田監督はしばらくの期間カメラを置いてしまう。「その時は、全くカメラを回さなくてイイやという風に思ったのですが、同時にそれで本当に良いのかな…という気持ちもあって、だいぶ気持ちが揺れ動いたんですが、最終的にはディレクター的な視点は捨てて、“自分が本当にカメラを回したいと思う時だけ撮る”ことと“父が撮られたくないと思うところは絶対に撮らない”という考えを自分自身に許したら、もう一度映像に向かうことが出来たんです」ディレクターとして良い画を撮ろうと思わなくなってから気負いなく撮れるようになり、最後の方は娘と撮影者、二人の自分が自然に共存していた気がする…と、砂田監督は語る。二人の自分とは勿論、娘としての自分と撮影者としての自分。撮る事を許容される瞬間の感覚が分かり始めて、気づけば自然にカメラを向けていたそうだ。

ただ、一箇所だけ砂田監督は、お母様から「二人だけにして欲しい」と頼まれたにも関わらず、そのまま固定されたカメラを回しっぱなしにしている。夫が初めて妻に向かって「愛している」と告げる場面だ。「やっぱりあの時は、(病室を出る)瞬間に“ここは撮るべきだ”と思ったんです。なかなか人には理解されにくいとは思うのですが、撮るかどうかの判断は、私なりのルールに基づいているんです」砂田監督は撮影していた時の自身について「私の基本は娘なんです」と語る。「娘としてその場にいて、ふとした瞬間に撮影者としての自分が現れる」それが前述した二人の自分が存在したという事なのだが、「緊迫した瞬間だから何でも撮っていたわけじゃないんです。二人の自分が折り合わないときは撮らないし、全ての状況が一致した時だけ回すという感じでした」そこが仕事でカメラを回している事と大きく違うという。とは言いつつも、やはり砂田監督は映像の世界に身を置いているだけにアングルやカット割りはプロの視点が入っている。「ディレクターとしては撮っていなかったのですが、どうしても、ここはズームしようとか、ここは家族も一緒に画の中に入れよう等と、考えてしまったのはありましたね」そこが簡単には説明しきれない不思議な状況なのだと砂田監督は語る。「私にとって映像というのはどんな形であっても第三者に観せるものだと思っているんです。例えば、家族だけで観るものであっても、世界中の人が観るものであっても、自分の中で作り方は変わりませんでした」
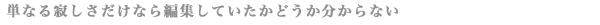
お父様の死後、今まで体験した事が無いほどの大きな喪失感を感じ、そんな気持ちをどう消化すれば良いのか分からず途方に暮れていたという砂田監督が編集作業に着手したのは葬儀から3ヶ月が過ぎた2010年4月の事。「父の最後の姿を間近でみて、どこか自分も一度死んでしまったような不思議な感覚があったんです。単なる寂しさだけなら編集していたかどうか分からない。自分は何か強いものを見てしまったという気持ちがあったから、それを自分の心が鮮明に覚えているうちに撮ってきたものを表現したいという思いが強くなったんです」そして砂田監督が、まず最初に行ったのは撮影したテープの内容を全て文字に起こす事だった。お父様は勿論、カメラに収まっている家族全員の一語一句を紙に書いて、それをベースにどのようにストーリーを展開していくかを構築していった。編集の段階で気をつけていたのはただひとつ…「どのような組み立て方をすれば、最後に大事な事が伝わるか…ただそれだけでした」という砂田監督が考えた構成は、前半は知昭氏の人物像を紹介する事に主軸を置き、後半はその時が近づいている知昭氏を在りのままに捉えた姿をメインとする事。「実は、その時も自分のために編集をしていたようなものなんです。そもそも、こういう話が映画やテレビになるなんて、私自身想像出来ていなかったので…」そんな砂田監督が完成した映像を是枝裕和監督に見せたのはその年の8月の事だ。「監督に見せたのも“ちょっと、こんなものを作ってみたんですけど見てもらえますか?”程度の感じだったんです(笑)」ところが、見終わった是枝監督が長い沈黙の後に発した言葉は“面白かった”だった。「“これは映画になるんじゃないか?”と是枝監督に言われても、ずっと半信半疑でした」その年の年末に配給会社が決定、劇場公開へ向けて最終的な仕上げが始まるのだが、それでも砂田監督は半信半疑の状態が続いていたという。
公開から4ヶ月が経った今でも多くのお客様が劇場に足を運んでいるという反響について砂田監督は最後にこう語ってくれた。「映画ってすごく強い力を持っていると思いました。自分の映画を世に送り出すというのは初めての事でしたが、ご覧になった方の人生のほんの一部でも心を動かすカケラを届けられたとしたら嬉しいですね。“人っていつかこの世を去るんだ”と、いう事を初めて実感して、自分の心の中だけにしまっておけなかった…というのが映画にしようと思った理由かも知れません。その気持ちが映画として表現できて、観客の皆さんに届いていたら良いと思います」
取材:平成23年12月27日(火)是枝裕和事務所にて

砂田麻美/Mami Sunada 1978年、東京都生まれ。
慶應義塾大学総合政策学部在学中よりドキュメンタリーを学び、卒業後はフリーの監督助手として是枝裕和らのもと映画制作に従事。主な参加作品に河瀬直美監督作『追臆のダンス』、岩井俊二監督作『市川崑物語』、是枝裕和監督作『歩いても、歩いても』、『大丈夫であるように Coco 終わらない旅』、『空気人形』など。第一回監督作品である本作で、第28回山路ふみ子映画賞文化賞、第36回報知映画賞新人賞他国内外の映画賞を受賞。


