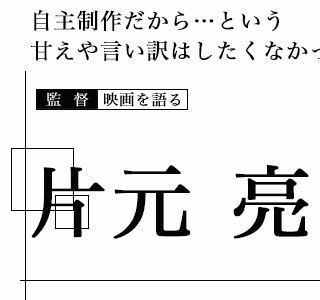|
誰でも簡単に映画が撮れるようになってから、飛躍的に映画館で上映されるインディーズ系の作品が増えてきた。奇抜なストーリーで勝負するもの、ユニークな切り口で日常を表現したもの、大手では作られないような発想力で、オッ!…と目を見張る秀作に出会う一方で、おいおいこれで金取るのか?と怒りを覚える作品も多い(それはデジタル技術が発達した手軽さの副作用とでも言うべきか)のも事実だ。そんな中、冒頭から、正にオッ!…と驚かされた映画に出会った。「インディーズどころか完全に自主制作、自主配給ですよ…アハハっ」と笑う片元亮監督が手掛けた長編サスペンス『ストロボ ライト』だ。住宅街の一軒家で発見される右手首の無い死体…警察の調査が進むにつれて事件は意外な展開を見せはじめる。驚いたのは冒頭の臨場シーンだ。規制線が貼られた現場に到着した主人公。そこは多くのマスコミと野次馬でごった返しており、とても自主制作とは思えない規模の映像を見せつける。当然、停まっているパトカー1台にだって結構高額のレンタル料が発生するのだから。「だって、事件現場にはパトカーがいて当たり前ですよね。お金が掛かるからパトカーは呼べないって諦めたら誰が一番残念に思うか?というと、観客の皆さんなんですよね。刑事ドラマなのにパトカーが出てねーよ…と思われたくなかったんです」片元監督は「自主制作だから…という甘えや言い訳はしない」というスタンスから、知恵や工夫でメジャー系にも引けを取らない映画を作ろうと挑んだのだ。 片元監督が本作の脚本を書き上げたのは、大阪芸術大学で中島貞夫監督に師事していた10年ほど前。「まだ師匠の弟子をやって間もない頃だったのと、作品の規模が大きかったので、今、これを作るのは無理だと思って、その時点では寝かせておいた企画なんです」その後、一度は映画から離れた時もあった。「しばらくは普通のサラリーマンをしていたのですが、どうしても映画が撮りたい!という衝動に駆られて、10分ほどの短編を作ったんです」これが片元監督のある意味ターニングポイントとなった。試しに応募した“インディーズ・ムービーフェスティバル”の短編部門でグランプリを受賞したのだ。そこで片元監督は脱サラして映画を撮る決意を固める。「その分、出遅れて既に30歳でしたから時間が無い。だったら劇場公開出来るクオリティーの自主制作映画を作ればイイんだ!って思ったんです」いやいや、言うのは簡単だが、それで映画監督になれるほど世の中は甘くない…はずだが、それを片元監督は実行してしまったのだ。端から見たら、いきなり無謀とも言える勝負に出た片元監督は、新しい題材を探すのではなく、勝負に出る時にやろうと思っていた10年前の脚本を引っ張りだした。「人生一回きりですから…やるなら大規模なもの。よく自主映画にあるような小規模の映画ではなく、これってメジャー?と思わせる作品を作ってやろうと『ストロボ ライト』を撮ったんです」 片元監督が最初に行ったのはロケ地の交渉。「実は僕の中では兵庫県伊丹市と決めていたんです」この街の景色に惚れて、この場所だったらどんな切り方をしても撮れる!と確信していた片元監督の行動は早かった。市にコネがあるわけでもないから、素直にこの街で映画撮りたいんですけどどうしたら良いですか?と地元の人に聞いたのだ。「そこで…面白い兄ちゃんいるな〜って言ってくれる人がいて、街のイベントを見においでよって、誘ってくれたんです。そこで色々な人と知り合いになり、その中の一人が、地域活性に造形が深い方で…だったらこの人に会った方が良いと電話してくれたんです」そこから話は、スムーズにまとまり始めた。いつの間にか二十人近くの有力者が集まり、こんな映画を作ろうと考えています…と説明会を開いた。何と企画に興味を示した街の人々はサポーターズクラブを発足して、協力体制を組んでくれたのだ。「多分、トップダウンでお願いしていたら無理だったと思います。市民の人から上に押し上げてくれたので話を聞いてくれたんじゃないかな?街の人たちが応援してくれて、映画作りを楽しんでくれる。この撮影がキッカケで友達になったという人たちがいるんです。撮影を通じて、街の活性化の一端になれたのは財産だと思っています」 ところで、この映画…伊丹市で全面ロケをしながら、物語は東京の設定となっている。実は、そこに片元監督なりの伊丹市に対する思いが込められている。「東京じゃないと映画が撮れないという風潮を覆したかった。人と街がタッグを組めば別の場所でも作れるよ…というのを証明したかったんです。そりゃ、細かい事言うと石垣が西日本と東日本では違っているとか(笑)でもそれは知っている人しか気づかないことですよね。ここで伊丹が舞台の映画を作ってしまったら、今後、伊丹が舞台の映画じゃないとロケに来てくれないじゃないですか」という片元監督の言葉を聞いて軽く衝撃を受けてしまった。その通りだ。ご当地映画を作ってしまうと一時は良くてもそれ以上は広がらない。しかし、伊丹でも東京の映画が出来ると証明すれば、東京から撮影部隊が来る事も想定出来るのだ。「伊丹市に行ったらこういう画を撮れるらしいぞ…ってロケに来てくれたら、伊丹市への恩返しになると思っています。だから伊丹市の観光地は画面に映っていないんです」 伊丹市の協力によって、自主映画とは思えない奥行きのある映像が誕生した。例えば、事故現場のシーンも公道で撮影すると警察の許可を取らなくてはならない。そこで、片元監督は工場に歩道の柵と垣根を並べて住宅街の道を作り上げたのだ。「映画は切り取る芸術なので…」確かにそうだ。フレームに収められている映像がしっかり作られていれば、見えない外側は観客が勝手に想像する。逆に肝心の映像がスカスカだと、観客はそこでシラケてしまってフレームの外にまで想像力は行かない。「観客にジョボイと思われたらオシマイなんです。お客様から入場料をいただいている限りは、自主制作だから甘く見てね…という言い分は通用しませんから」だからこそ片元監督は「あとは企業努力と知恵です」とキッパリと言い切る。例えば、他のシーンで登場するパトカーは、伊丹市で持っている青パト(地方の市役所が持っている青いサイレンのパトカーに似た公用車)を借りて、サイレンをCGで赤に変えたという。またクライマックスとも言える冷凍倉庫のシーンでもひとつのセットに、カットごとに段ボールの配置を細かく変える視角を計算したアイデアで、広い空間を作り上げることに成功している。「僕以外、スタッフも出演者もどう撮られているか分からなかったと思いますよ。本当にパズルみたいな撮影でしたね」いいものを作ろう…じゃあどうしたらよいか?それは、知恵だけじゃない。好きである事と発想が両立しなくてはダメなのだろう。 もうひとつ、自主映画として異例なのは、セリフがある登場人物だけでも47名という数の多さだ。主要な役は全てオーディションで採用したプロの俳優だが、最も多くの登場人物が一同に介する捜査会議のシーンで、背後に映っている大半が伊丹市のエキストラだ。「群衆シーンでは、主要メンバー以外は全部エキストラなんです。伊丹市の人って皆さん芝居するんですよ(笑)自由に動いてくださいって言っても普通は立ったまま、どうしていいか分からないものじゃないですか。でも伊丹市の人たちは、ある程度、導線を付けたら皆さん芝居されるんですよね」片元監督が、エキストラにお願いしたのはただひとつ…しゃべっている時には関西弁禁止(笑)ということだけだった。「座り方や歩き方のコツをアドバイスすると皆さん飲み込みが早いですよ」時には撮影見学に来た市民を飛び込みで野次馬として参加させてしまう事もしばしば。「街の人に楽しんでもらって僕らも楽しみながら撮れたらイイな…と思いながら撮影していました」 数多くのプログラムピクチャーを手掛けた中島貞夫監督に師事した片元監督は、「映画は平面ではなく上下、前後、奥行きで構成されている。自主映画はどうしても横の動きになってしまいがちだが、縦や上下の演出が出来るようになったら一流だ」と言われた事を今でも覚えているという。「完成後に槇から、登場人物の動かし方が中島監督の“あゝ同期の桜”と似ているシーンがあって、“やっぱりお前弟子なんだね”って言われたんです。僕は意識していなかったけど、きっと人の動かし方を知らず知らずの内に身に付いてたんでしょうね。特に師匠から何かを教えられたわけでもなく、自分の作品を編集している時も“お前、もっと映画観ろよ”だけでしたから」何度も中島監督からダメ出しをされて、時には、もっと人を見ろ!バカヤローと怒鳴られた事もあったという。「自分としては何がダメだったんだ?って悩むわけですよ。師匠の背中を見て何かを汲み取ろうと必死でしたね」そんな事を繰り返していたある日…「自分が編集したフィルムを見ていたら、あぁ〜そういう事か!って突然、気がついたんです。作業途中だった作品を全部バラして一気に繋ぎ直して持って行ったら、師匠から…片元分かってきたじゃねえかと言われたのが、忘れられません。僕の中でつかんだ瞬間だったんですよ。そこからが早かったですね」 平成22年8月から始まった撮影は翌年4月に終わり、平成25年から伊丹市を中心として関西先行で公開された。そして、いよいよ今年から全国巡回を開始して、全て自分たちでプレスシートやパンフレットを作って(驚くほどのクオリティの高さ!)宣伝を担当する槇徹氏(何と監督の思いに賛同して会社を辞めて、この映画のために駆けつけたのだ)と二人三脚で、ひとつひとつ自らの足で映画館を開拓している。今、片元監督が振り返って思う事は「映画を作る前から、これは無理なんじゃないか…って、フタをしている人たちが多いように思えるんです。始めからフタをとっぱらって、お客さんに楽しんでもらうには何が必要か…それを一番に考えれば、日本映画は、もっと大きく面白くなるはず。僕の映画を観て、こんな事も出来るんだったら自分もやってみよう…と思ってくれればイイんです」 取材:平成27年6月2日(火) 横浜シネマリンロビーにて 片元 亮/Ryo Katamoto 1977年、山口県生まれ。 2000年に大阪芸術大学映像学科卒業制作作品『Si:(シー)』において、脚本・編集・監督を担当。卒業後、同大学大学院に進み、修士課程作品『つたえたいことがあるんだ』を制作する。その後、いくつかの作品に携わり、2006年に制作した短編自主映画『キラキラ』が、第10回インディーズムービー・フェスティバルTANPEN部門でグランプリを受賞。 |
|
|
Produced by funano mameo , Illusted by yamaguchi ai
copylight:(c)2006nihoneiga-gekijou |