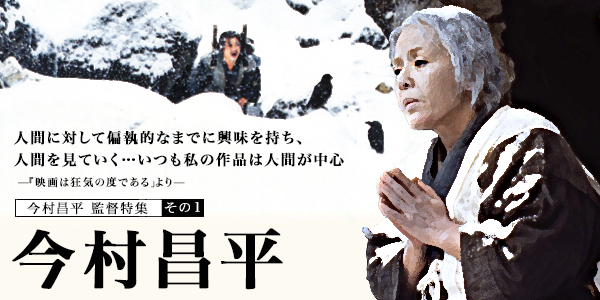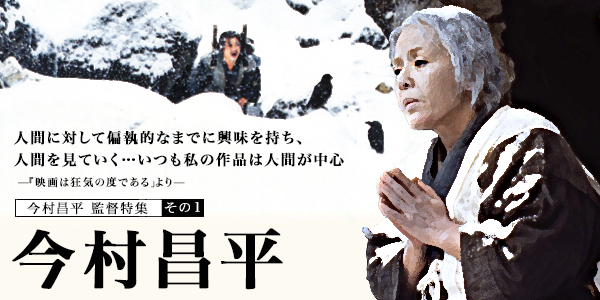

「俺は死ぬまでウジ虫ばかり画く」とは…『豚と軍艦』のシナリオを書いていた今村昌平監督に、松竹時代の師匠である小津安二郎監督と脚本家の野田高梧から「汝等何を好んでウジ虫ばかり画く?」と言われた時に、カッと頭に血が上って決意した言葉だ。今村監督が松竹から日活へ移籍して作品を作り始めたのが、昭和33年の『盗まれた欲情』から。ウジ虫ばかり…と言っても、今村監督は、社会を批判するメッセージ性の高い映画にしようという製作意図は全く無く、弱者がしたたかに生きている様の滑稽さや可笑しみだけを追求した、あくまでも娯楽映画に徹している。言い方は悪いが、「しょうもない人間たちに焦点を当てて、その生態を笑ってしまおう」という邪心なき悪意に満ちたもの(サディスティックでもある)があるのだ。だから面白い。不思議なのは、最初は、その映画で描かれている登場人物たちの言動に失笑していても、物語が進むにつれ、いつの間にか圧倒され引き込まれている事だ。特に日活から独立プロを立ち上げた頃の作品に顕著に表れているところに、今村監督が真に作りたかった映画を模索していたのがよく分かる。題材とした昭和30年代後半という時代に生きていた人間が面白いのか?ともかく今村監督が乗りに乗っていた作品が、戦後の混乱期を生き延びた人間たちのパワーを宿したかのように生き生きと存在していた。そして、その時代と変わらぬ混沌が未だに存在し、人知を越えた事件が多発している現代…今村監督が生きていたら、どんな映画を作るだろうか?と考える。

そんな人間たちを描いているから今村監督の映画は確かに汚い。人間のドロドロした部分のもっと奥深いところにある精神まで落とし込む。今村昌平が共感する坂口安吾の「堕落論」に書かれている「人間が変わったのではない。人間は元来そういうものであり、変わったのは世相の上皮だけのことだ」という言葉が映画作りの根底にあるのだ。社会がいくらキレイになったとしても人間本来の汚さは変わらない…という事か。黒澤明監督の『酔いどれ天使』を観て、芝居にしか興味がなかった今村昌平が映画監督を志そうと決めたのも正に安吾の時代でもある。決して戦争という時代が人間の狂気を生み出したのではなく、狂気に走った人間は元々持っている資質が表面化しただけであり、それであれば時代が変わろうともウジ虫のような人間は、いつでも存在する事となる。ウジ虫を主役とした最たる作品と言えば『復讐するは我にあり』が真っ先に思い出されるが、実在した連続殺人鬼よりも、筆者はむしろ『人間蒸発』に出てくるような奥底に潜む虚栄心やエゴをさらけだすネズミこと早川佳江のような一般人や、『楢山節考』に出て来る村の掟という因習に縛られ、その掟を破った者に情け容赦ない制裁を加える村人たちにこそ、剥き出しにされた本質の中に薄ら寒いウジ虫(小津監督の言うウジ虫とは、社会のクズ的な意味ではなく、弱者…今でいう負け組)の姿を垣間見る。今村監督は自身の著書「映画は狂気の旅である(日本図書センター刊)」のまえがきにて、何が面白くて映画を撮るのか?強いて言うなら人間の面白さ…と述べている。人間を「つかみがたい不定形の生き物」と形容し、その生き物を分析、構築する事に無限の面白さを感じる今村昌平の原点は、敗戦後の闇市で過ごした体験にあるようだ。そこでは、人間が生きて行くためにありとあらゆる悪業が行われ、正に人間の本質がヘドロのようにうごめく、戦争の吹き溜まりのような場所であったろう。

『豚と軍艦』を製作していた頃は安保闘争真っ只中で、早稲田出身の今村監督とて、決して無関心では無かったが、「イデオロギーや政治よりは、人間を泥臭く追究する方が性に合う。日本の社会を考えるなら、土着の文化、風俗から迫る方が理にかなうように思い始めていた」と、語っているように、敗戦後の日本…いや日本人が、どこに進むべきか?を問う前に、日本人の根底にある汚いものも含めて引っぺがし、剥き出しにしたのである。現代日本人の社会や価値観がどのように形成されたのかを農村に古くから根強いている俗信や因習から掘り下げる。戦後、アメリカ主導による民主主義は、大都市や上辺だけのものであり、現在、連日ニュースで賑わしている猟奇的で凄惨な事件は、日本人に刻まれている土着的DNAそのもののように思えてならないのである。今村監督は、役者の演技が邪魔になってドキュメンタリーこそ人間の面白さを描ける唯一の手段…と、活路を見出そうとした時期もあった。そこで『人間蒸発』や『にっぽん戦後史 マダムおんぼろの生活』という名作が生まれたにも関わらず、自身が心底満足している結果に至っていない。

また、今村監督は、戦後の日本が豊かさを追求する陰で、国家から見棄てられた人々を称した「棄民」にも目を向けている。その殆どが独立プロを立ち上げてから手掛けたテレビのドキュメンタリーであるが、松竹から日活へ移籍して最初に手掛けた『盗まれた欲情』で描かれるテント劇場と呼ばれる簡易小屋で芝居を打っている一座の話しだった。場所代を払えず追い出されてしまった一座が、根無し草の如く、田舎町から田舎町へと転々と興行をする姿は、まるでロマのようでもあり…一見すると自由に生きていると捉える事も出来るのだが、彼らの狭い世界にも日本特有の土着性が存在している描かれ方を、既にされていたのが興味深い。炭鉱街で暮らす職を失った在日韓国人の兄弟を描いた『にあんちゃん』では、炭鉱が次々と閉山されていた時代に、肩寄せ合って生きていた幼い兄弟たちの面倒を見る街の人々を笑いとペーソスを交えて描く…今村監督としては珍しい変化球の人情ドラマであったが、ここで描かれている人々も新しいエネルギー政策によって切り捨てられた「棄民」であった。
今村監督が井伏鱒二の原爆投下後の広島を題材にした『黒い雨』を製作すると発表された時に、「今村監督が何故、広島を取り上げるのか?」という意見が出た事に筆者は強い興味を持った。現代でこそ広島・長崎は核廃絶を唱える上で負のシンボルとして掲げられているが、戦後数年に渡って研究する事は勿論、被爆者に対して日本人同士であるにも関わらず、言われなき差別を受けていた。これは明らかに「棄民」であって、日本人の根底に流れる土着的な精神によって生まれた闇の部分が描かれていた。そういった意味においても今村監督が本作を取り上げたのは当然の事であり、逆に疑問の声が上がる方が不思議でならなかった。また、『カンゾー先生』のシークエンスで、戦時中の貧困と餓えに喘ぐ孤児の妹弟が、麻生久美子演じる姉に「腹減った、淫売頼む」と書かれた一枚の紙を渡す場面が印象的だ。島で男に体を売って日銭を稼いでいた娘を診療所に雇って淫売を止めさせていた柄本明演じる診療医が苦虫を噛んだ表情を浮かべるところに今村監督らしいアイロニカルな笑いを誘う。それを明確に描いた(沖縄返還前に石垣島でロケを敢行した)『神々の深き欲望』は、自ら集大成のつもりで製作したと語るだけあって、閉鎖的な島を縮尺された日本に見立て、国家と民族の在り方をアグレッシブに問い続けてきた最も今村監督らしい作品として仕上がっていた。
こうした家族や村という閉鎖された世界におけるヒエラルキー的な集団(組織)の在り方について、『楢山節考』で姥捨伝説をベースとして更に発展させている。『にっぽん昆虫記』の貧しい女工の娘が戦後、生きていくために身を売り、売春組織の元締めにまでなる左幸子演じる松木とめも、『赤い殺意』の男に犯され続けている内に、ある種の自我が芽生え、女になっていく東北の封建的な田舎町に嫁いだ春川ますみ演じる高橋貞子も「棄民」と位置づけても良いかも知れない。敢えて見ないフリを続けてきた日本人に突きつける生々しい「もう一人の日本人の姿」に我々観客は、ただただ驚愕するしかない。人間って、どうしようもない生き物だけど、なんと愛おしいものなのだろうか…と、感じさせてくれる…だから今村昌平の映画は面白いのだ。
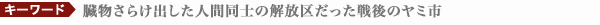
「ヤミ市と赤線と読書とで、私の戦後は充実しており、たまに戯曲を書いて仲間に叩かれても、なにいずれ傑作を書くのだと決め込み、大して消沈しなかった。失恋しても、ヤミ市で意識失うほどカストリ(臭くて強い粗悪な焼酎)を浴びると、もうそこは私にとって自由の小天地であり、失恋の苦さを、一種の余裕で噛み締めることが出来た。(『遥かなる日本人』岩波書店刊)」…と、今村監督は自身にとってのヤミ市についてこう述べている。確かに今村監督作品を振り返ると、ヤミ市で体験した、安酒と汚水の匂いが入り混じった吹き溜まりのような場所で生きる人間たちとの関わりが多大に影響を与えたであろうと見て取れる。
日本では大正12年の関東大震災後、東京近郊で露天市が出来て、これがヤミ市の原点といわれている。また昭和14年に発せられた価格等統制令によって、産業資材や生活物資が公定価格に一本化され、物価が商工省下の価格形成委員会により決定されるようになると、配給の不足を補うためのヤミ市が形成されるようになった。今村監督が体験したヤミ市とは、戦後連合国軍占領下の日本の混乱期に成立した商業形態である。なおこの種の市場は終戦直後は「闇市」と蔑称で呼ばれたが、その後国民生活に必要であると認識され「闇」という漢字を排除して「ヤミ市」と表現されるようになった。
終戦直後の日本では、復員や引揚げなどで都市人口が増加したことで政府の統制物資が底を突き、物価統制令下での配給制度が麻痺状態に陥り形骸化していた。そのため都市部に居住する人びとが欲する食料や物資は圧倒的に不足。食料難は深刻を極め昭和20年の東京の上野駅付近での餓死者は1日平均2.5人で、大阪でも毎月60人以上の栄養失調による死亡者を出した。昭和22年には法律を守り、配給のみで生活しようとした裁判官山口良忠が餓死するという事件も起きている。
ほとんど全ての食料を統制物資とした食管制度のもとでは、配給以外に食料を入手することは違法行為だったが、一般の人びとは、満員列車に乗って農村へと買出しに出かけ、米やサツマイモのヤミ物資を背負って帰った。この光景は今井正監督の『ここに泉あり』(昭和30年)の冒頭で車両からはみ出さんばかりの乗客が詰め込まれた列車が高崎駅に滑り込んで来るシーンで象徴的に描かれている。また、荒井晴彦監督の『この国の空』(平成27年)では、工藤夕貴と二階堂ふみ演じる母娘が知り合いのツテを頼って地方の農家まで着物と交換に訪れるシーンがある。そこでは高飛車な農家の主人に二人は頭を下げて、分けてもらっている…という立場の格差が描かれていたが、このように食料を生産していない都市の住民は、ヤミ物資に頼らなければ飢え死にしかねなかった。中には市川崑監督の『獄門島』(昭和52年)に出てくる三谷昇演じる復員詐欺のような、地方の名家に、御宅の息子と戦友で間もなく戻ってくる…と嘘を伝えに来て、御礼の食料をせしめるという輩まで横行していた。
このように食料物資は絶対的に足らず占領軍の援助があったものの、配給の遅配が相次ぐ事態に陥っていた。配給制度がゆらぎ、人びとは買出しやヤミ物資の購入でようやく糊口をしのぐものの、日々の食事は雑炊が続き、米よこせ運動が各地で勃発した。このような状況の下で、戦時中の強制疎開や空襲による焼跡などの空地でヤミ市がはじまった。敗戦の4日後の昭和20年8月20日、新宿駅東口に開店した露天市がヤミ市の第1号となった。正に早稲田大学に入学が決まっていた今村監督が通っていたヤミ市はここである。ナベ釜、履物、衣料、粗悪な大工道具から食料まで食管法の統制化にありながら、金さえ出せば何でも買える場所だった。早稲田の学生だった今村監督は家庭教師の月謝の代わりに朝鮮人が造った焼酎を現物支給で貰い、それを新宿のマーケットにある飲み屋に売って生計を立てていた。ちなみに現金で月謝を貰うよりも遥かに儲かったらしい。
闇市は日本各地の都市部に同時期に発生し、東京では新宿東口から新宿通りにあった。昭和26年10月25日に麦の統制撤廃が閣議決定され、米以外の食品は自由販売となりヤミ物資ではなくなった。そしてその年、東京都内の常設露店は廃止となり、いわゆるヤミ市は姿を消した。現在では闇市の多くは商店街や繁華街となっており、新宿西口の思い出横丁、歌舞伎町の新宿ゴールデン街、中野の中野サンモール、上野のアメヤ横丁、下北沢の駅前食品市場、吉祥寺のハモニカ横丁、大阪の鶴橋商店街、大阪の五階百貨店、神戸の元町高架通商店街などが当時の面影を今に残している。「ヤミ市には、ガメツク生きようと、ぼんやり生きようと、生き物としての人間の臭いが立ち込め、年齢や階層に関わりない、暗黒の中の自由みたいな、血管の中にドロリ坐りこんでいる気軽さみたいなものがあった。あらゆる悪徳がひしめいて在りながら、臓物さらけ出した人間同士の解放区でさえあった。」今村監督がヤミ市について述べている言葉が実に興味深い。

今村 昌平(いまむら しょうへい )SHOHEI IMAMURA
1926年9月15日〜2006年5月30日 東京府東京市大塚出身
耳鼻咽喉科の開業医の三男一女の三男として生まれる。
1944年に東京高等師範学校附属中学校(現・筑波大学附属中学校・高等学校)を卒業。徴兵を避けるため桐生工業専門学校(現・群馬大学工学部)に入学、終戦後直ちに退学し、早稲田大学第一文学部西洋史学科に編入。在学中は演劇部に所属し演劇活動を行っていた。卒業後、松竹大船撮影所に入社。主に小津安二郎の助監督をつとめ、松竹大船助監督部幹事になったが、1954年に日活に移籍する。1957年の川島雄三監督『幕末太陽傳』や浦山桐郎監督の『キューポラのある街』の脚本を経て、1958年に『盗まれた欲情』で監督デビューする。田坂具隆の代役で監督した1959年の『にあんちゃん』では文部大臣賞を受賞した。撮影にあたっては基本的にオールロケが原則で、俳優もスタッフもロケ地で長期間の合宿生活をして暮らしながら撮影したり、アフレコを嫌って臨場感のある同時録音にこだわるなど妥協のない粘りの演出から鬼のイマヘイと呼ばれていた。脚本執筆の際には徹底した調査を行い、1963年の『にっぽん昆虫記』では売春婦とその斡旋業者に取材したノートは3冊になった。続く『赤い殺意』を最後に日活から独立。1966年3月に独立プロ「今村プロダクション」を設立する。1975年には、横浜放送映画専門学院(後の日本映画大学)を開校し、三池崇史や佐々部清ら多くの映画監督を輩出した。1979年に発表した『復讐するは我にあり』は日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞し大ヒットを記録した。1983年の『楢山節考』はカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞。1997年の『うなぎ』では、2度目のカンヌ国際映画祭のパルムドールを受賞している。2006年5月30日、転移性肝腫瘍のため東京都渋谷区の病院で79歳で死去。遺作は『11'09''01/セプテンバー11』中の短編だった。
 |
 |
【参考文献】
映画は狂気の旅である 私の履歴書
200頁 19.2 x 13.2cm 日本図書センター
今村昌平【著】
1,944円(税込) |
 |
 |
【参考文献】
遥かなる日本人
324頁 16 x 11.1cm 岩波書店
今村昌平【著】
|