

大林宣彦監督を語る時、尾道という瀬戸内海にある小さな港町を避けるわけにはいかない。海に面して陸地が山になっており、家々は傾斜地に建っている。一年を通して温暖な気候に恵まれたこの地で生まれ、幼少期から多感な青春時代を過ごした大林監督が「尾道三部作」「新・尾道三部作」を作ったのは必然的な流れであった。代々続く医者の家系に育ちながら、医学の道を歩まなかった理由。ある日家に置いてあったブリキ玩具の活動大写真機とセルロイドのフィルムとの出会いから“動く絵”の虜となってしまう。これが映画監督・大林宣彦の原点だ。
『転校生』のオープニングで尾美としのり扮する主人公・和夫が尾道の風景を8ミリで撮影したモノクロの映像から「尾道三部作」はスタートする。勿論、この頃は尾道という小さな町が三部作になるなんて大林監督自身思いもよらなかっただろうが…。本作で初めて尾道を目にした時、何故か懐かしく思った。多分、筆者の祖父母の家が小さな漁師町にあり木造の家が密集した路地をぐるぐると駆け抜けて遊んだ幼少期の記憶が蘇ったのかも知れない。『転校生』の中に出てくる路地も海が映っていなくても(『転校生』は海の映像は出てくるのだが路地裏の印象が強い)潮の香りが漂ってくるのは木造家屋の板に潮がこびりついているからだ。当時の尾道は新幹線が停まらないし、勿論今みたいな観光地化もしていない寂れた町だったと後に語っている。大林監督は「心ゆくまで自分の映画を作ろう」という極めてパーソナルな立場で子供の頃に歩き回った路地裏や坂道、石段…そして崩れかけた土塀をありのままに撮影したという。なるほど!それで前述した思いが溢れた理由が分かった。『転校生』のカメラの目線は我々観客と同じ目線だったのだ。「角を曲がったらいるんじゃないかなと思った少女の気配」(「ぼくの映画人生」より抜粋)そうだ、そうなのだ。子供の頃、そうしたドキドキ感の中で生きていたのだ。単なる観光地を紹介するようなキレイな風景ばかりを撮っていたら、この作品は名作と成り得なかっただろう。まさに、日本の子供たちの原風景が『転校生』の中に存在していたのだ。ユニークなのは完成披露を尾道で行った時、尾道の美しい風景が全く出て来ない事に大人たちはかなり難色を示したという事実。確かに映し出されるのが観光マップに載らない薄暗い路地や軒先では観光客は呼べないと思ったのだろう。まさか公開直後から「映画を観てやって来た」という若者が大挙して来るなどとは夢にも思わなかったのだろう。
映画のヒットと共にその反響たるや、ある種の“尾道ブーム”を呼び起こした大林監督の元に「もう一度、尾道を舞台にした映画を作って欲しい」というオファーが入る。こうして出来たのが角川映画の『時をかける少女』だ。前作が大林監督のパーソナル作品だとしたら本作は角川春樹のプライベート作品と言っても良いだろう。まだ世に出る前の原田知世のためにどうしても映画を作りたいという思いから大林監督に話を持ちかけたのだ。ただ厳密に言うと本作の舞台は尾道が半分、隣町の竹原半分という割合で撮影されており『転校生』のように100%純粋な尾道映画ではない。ところが、竹原の江戸時代から続く古い街並みに対して尾道はファンタジックな小道や家が建ち並ぶ町として見事なコントラストを醸し出していた。原田知世演じる芳山和子の屋敷や深町家のラベンダーの香りが漂う温室、そしてファンの中で最も人気の高い色とりどりのタイルが敷き詰められたタイル小路等…三部作中一番ファンタジー性が強い作品だけに違った尾道を見る事が出来る。そして「尾道三部作」の頂点と言える富田靖子主演の『さびしんぼう』が公開されるやいなや尾道の認知度は一気に加速し日本で一番有名な小さな町となった。タイトルの語源は尾道あたりで愛すべきガキ大将を“がんぼう”(きかん坊の事?)と呼んでおり、少年時代の大林少年は“がんぼう”と呼ばれる度に悔しくて、その悔しがる自分の事をいつしか“さびしんぼう”と呼ぶようになる─言わば大林監督の造語なのだ。『さびしんぼう』の企画を持って尾道にある行きつけの喫茶店“TOM”に立ち寄った大林監督は、そこに設置していたノートの中に“「尾道三部作」を見たい”という言葉がたくさん書かれているのを読んで初めて三部作にしようと決意したという。『転校生』の原作者・山中恒の“何だかへんて子”をベースとした『さびしんぼう』が具体化した瞬間である。初めて港町としての尾道の情景を映し出した『さびしんぼう』(驚く事に前二作には海は出て来ても港の印象が殆ど無い)は、主人公の少年が憧れる美少女が通学で利用するフェリーを効果的に使っていた。実は尾道に行くまで、今ひとつ掴めなかった島との距離感が意外と近い事と、フェリーの本数が都会の地下鉄以上の頻度で行き交い、乗船料も100円程度と格安なのにビックリした。映像では長い時間が掛かっていたように思われた乗船シーンは、もしかすると…船で数分の距離にある島が遠く感じていた少年の心境を表した結果なのだろうか?撮影にはフェリーを一隻チャーターして、更に向島や因島といった対岸でのロケーションを行う等、海の向こうの尾道という映像が印象的だった。

大林監督は尾道を「少年の町」と地元の観光マップで述べている。一連の尾道作品を観比べてみると、ナルホド確かにその通りだ。「新尾道三部作」の二作品は少女が主役でありながらカメラの目線は年上のお姉さんに憧れを抱いている少年のようでもある。自動車事故で亡くなった姉の幽霊に励まされ成長していく妹を描いた『ふたり』は一見、赤川次郎の原作だけに乙女チックな作品なのだが石田ひかりや中嶋朋子演じる姉妹は少年が思い描く理想の女の子像にも見える。旧三部作から6年、本作を観た時にどこか違和感を覚えた記憶があった。ずっと考えていたのだが最近になってその理由が分かった。旧三部作は尾道の観光地以外の場所をロケ地に使っていたのに対して、『ふたり』は尾道の観光名所や新しく建ったホール、女の子が好きそうな喫茶店(ロープウェイの近くにあるワッフルが美味しい“喫茶こもん”は一躍有名になった)が随所に出てくるのだ。まるで雑誌Hanakoで特集を組めそうな程。山頂にある文学の小路から港を一望する光景やヨットハーバーのレストランを見て憧れた女子は果たして何人いたことか…。本作の主人公が現代の姉妹だからオシャレな雰囲気の場所を選んだ…というのも理由としてあるだろうが、一番の要因は尾道という町自体が旧三部作から(言いかえれば旧三部作のおかげで…)変わってしまったのではないだろうか?6年前に残っていた風景は本当の意味でノスタルジックな風景になってしまったのだ。
二作目の『あした』では遂に半分以上を尾道から近隣の島に舞台を移している。三ヶ月前に沈没したフェリーで家族を亡くした遺族の元に死者たちからのメッセージが届く赤川次郎の神秘性の深いファンタジーには尾道は発展し過ぎてしまったのだろう。後半の殆どが百島や向島で撮影が行われ、尾道の印象は希薄になっているもは確か。「深夜0時に呼子浜に来て…」というメッセージに引き寄せられた遺族たちが、ある者は自家用ボート、ある者は島々に架かる橋を渡って島に向かう。まるで川のように見える尾道水道という、れっきとした海を血管のように結ぶ橋が重要な役割を担っているのは大林監督作品としても珍しい。なるほど『あした』は、“尾道の道(水路も含めて)”の映画なのだ!宝生舞が自転車で駆ける海沿いギリギリの百島の岬や向島にある兼吉の丘といった様々な表情の道が出てくる。たった数時間だけ生前と変わらぬ姿で会いに来る切ない物語は、確かに瀬戸内海の風土がよく合っていた作品だ。そして、「新尾道三部作」の完結編『あの、夏の日〜とんでろ じいちゃん』には、満を持して原点に立ち戻った郷愁をそそる昔の尾道の風景が出てくる。小林桂樹扮するおじいちゃんが住む尾道にやって来た男の子が体験する不思議な夏休みを描くファンタジーだ。このおじいちゃん…子供の頃にタイムスリップ出来る能力を持っているという設定のため、大林監督はまだ砂浜が残っていた時代の尾道をCGで作り上げてしまった。更に、開発という名の下に町や自然の景観を破壊するバブル以降の風潮に対するアンチテーゼとして尾道に架かる二つの橋を見事に消し去ってしまった。本作を最後に大林監督が尾道で映画を作っていないのはバブルの崩壊と共に尾道の原風景が失われてしまったからかも知れない。尾道は今のままであって欲しいというのは余所者のエゴだろうか?
最後に大林監督が尾道に対して送った言葉で締めくくりたいと思う。「旅の中で、ひとは大人になっていく。本当に上手に大人になるということは、その少年の心を上手に保存し、人生の中に持続していく知恵と工夫のあることだ。ひとはそのために旅をするのであり、尾道もまたそういう旅人の心に答えながら、上手に大人になっていきたいものだ。尾道には、少年の心がよく似合う。その古里をぼくは何よりも誇らしく思っているのだから。」(尾道市観光協会「おのみちロケ地案内図」より抜擢)
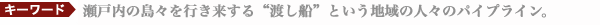
広島県尾道市の市街部と向島の間にある尾道海峡と呼ばれている尾道水道には4航路(福本渡船、向島運航、尾道渡船、宮本汽船)が、5〜10分感覚(都心の地下鉄やバス並の間隔)で往復している渡し船がある。乗船料は大人60円〜100円で車両の場合はプラス90円〜380円、自転車はプラス10円とかなり安い金額だ。終発が22時台の便まであるため住民たちにとっては重要な交通網と言っても良いであろう。『さびしんぼう』では、主人公ヒロキが片思いの少女・橘百合子の故障した自転車を押して、彼女の住む向島まで送り届けるシーンで渡し船が重要な役割を担っている。夕焼けでオレンジ色にキラキラ光る水道を背景に自己紹介し合う二人だが、対岸まで500メートルにも満たない距離をたった3〜4分で結ぶ乗船時間は二人には短過ぎたのかも知れない。中でも土堂渡し場と向島町兼吉を結ぶ尾道渡船は、尾道と向島を結ぶ渡船の中で最古といわれる航路であり、江戸時代の書物に登場する。人や物資の輸送とともに、不審者の島内への侵入を阻む警備の側面も大きかったといわれる。そもそもは「兼吉(かねよし)渡し」と呼ばれた。往時には「本渡し」とも称され、今も昔も尾道の渡船の代表格である。かつては尾道市と御調郡向島町(2005年3月28日に尾道市に編入された)が設立した一部事務組合 公営尾道向島渡船事業組合によって運営される公営の渡船であったが、1984年11月1日付けを以て、事業をすべて譲り受け、尾道渡船株式会社として営業を開始。公営時代の名残で「公営渡船」と言っても地元では通じる。
ここ尾道港の歴史は、瀬戸内海の中央に位置する尾道港は背後に浄土寺、西国寺、千光寺の三山を控え、前面に尾道水道をへだてて向島と相対する往古からの天然の良港として栄えた。縄文、弥生の遺跡高須町の太田貝塚は原始時代すでにここに半農半漁の生活が営まれていたことを示すもので、当時の尾道港や松永湾の姿をしのばせるものがあるという程だ。聖徳太子の開基とも伝えられる浄土寺は、このころすでに尾道が港として使われていたことを示しており、延喜元年には菅原道真公が西下の途次尾道に立ち寄られた伝説がある。嘉応元年に入って備後大田庄地区からの年貢米貯蔵地として船津倉敷地に申請、指定され、尾道から船で各地へ搬送されるようになった。足利幕府の時代には大陸との貿易が盛んに行われ、特に和寇の根拠地であった因島、弓削、生名、佐木各島に近い関係から、対外貿易品の売買も行われ海運業者等の活躍の拠点となる。江戸時代は帆船の港内輻輳に伴い、港が狭隘となったので時の町奉行平山角左衛門により築港計画がたてられ、寛保元年に住吉浜を埋立て係留施設を築造して今日の港の基礎を形成した。その後、大正14年に尾道鉄道が市村に延びたのを契機とし、自動車交通の盛況とあいまって港勢も発展し、昭和2年11月には尾道港は、第2種重要港湾に指定され、同年12月開港場となり、13ヵ年の継続事業をもって改修工事に着手、昭和14年に東西御所に至る尾道水道を水深7.5メートルに凌渫し、西御所岸壁および浮桟橋等が完成した。昭和62年度に尾道糸崎ポートルネッサンス21調査地区に指定され、尾道水道のウォーターフロントに存在する老朽化し、機能の低下した港湾施設を、潤いのある港湾空間の創造を目標に、旅客ターミナル施設、港湾業務施設を中心とした尾道地区の再開発構想が策定され、現在に至っている。(参考資料「尾道市港湾振興課」ホームページより抜粋)

大林 宣彦(おおばやし のぶひこ)NOBUHIKO OOBAYASHI 1938年1月9日生まれ。
広島県尾道市東土堂町で代々続く医家の長男として生まれる。3歳の時、自宅の納戸の中で見つけたブリキの活動写真機と、戦争中ゆえ弦が供出されて音が出なかったピアノとの二つの出会いが生涯を定めた。この時、フィルムに絵を刻んで作ったアニメーション『マヌケ先生』をもとにして後に三浦友和主演でテレビドラマ、映画が制作される。18歳で上京し、慶應義塾大学医学部を受けるも、受験を途中で放棄して「医者になるつもりはありません。ぼく映画を作るよ」と父に告げ、浪人生活を経て、1956年に成城大学文芸学部芸術コース映画科に入学。在学中から8mmで作品を発表。1960年に大学を中退し、1963年に初の16mm作品『喰べた人』でベルギー国際実験映画祭で審査員特別賞受賞。『尾道』、『中山道』、『食べた人』、『Complexe=微熱の玻璃あるいは悲しい饒舌ワルツに乗って 葬列の散歩道』、『EMOTION=伝説の午後=いつか見たドラキュラ』などがアングラブームに乗って反響を呼ぶ。1964年に開館した新宿紀伊國屋ホールの開館イベントとして「60秒フィルムフェスティバル」を企画し、1960年代からは草創期のテレビコマーシャルにCMディレクターとして本格的に関わる。大林の手がけたCMは、チャールズ・ブロンソンの“マンダム”、ラッタッタのかけ声で話題を呼んだ“ホンダ・ロードパル”のソフィア・ローレン、“ラックス化粧品”のカトリーヌ・ドヌーヴ、などを起用して海外スター起用のCMの先駆けとなった。10年間で製作したテレビCMは2000本を越え、テレビCMを新しい映像表現として確立したとされる。
1977年の『HOUSE』で、商業映画を初監督。ソフト・フォーカスを用いたCF的映像、実写とアニメの合成など、さまざまな特撮を使って見せる華麗でポップな映像世界は世の映画少年を熱狂させた。1982年、自身の郷愁を込めて尾道を舞台とした『転校生』を発表。『時をかける少女』、『さびしんぼう』と合わせ"尾道三部作"として多くの熱狂的な支持を集め、ロケ地巡りのファンを増やした。また、大林はこれまで主に、新人アイドル・新人女優を主役にした映画作りを行ってきたが、特に1980年代に手掛けた作品は「80年代アイドル映画」というジャンルとしても評価される。近年は講演活動やコメンテーターとしてのテレビ出演、雑誌インタビューなども多い。2004年春の褒章に於いて紫綬褒章を受章しており、そして2009年秋の叙勲で旭日小綬章を受章した。受章理由は「長年にわたる実験的で独自の映画作りに」と伝えられたという。
(大林宣彦 公式ブログ http://fotopus.com/naviblog/ohbayashi/)
 |
 |
【参考文献】
ぼくの映画人生
280頁 19 x 13.8cm 実業之日本社
大林宣彦【著】
1,785円(税込)
|
 |
 |
【参考文献】
A MOVIE・大林宣彦 ようこそ、夢の映画共和国へ。 (シネアルバム)
223頁 21 x 14.8cm 芳賀書店
石原良太、野村正昭【編集】
|


