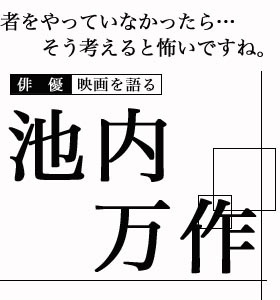|
父親に俳優であり映画監督として一世を風靡した伊丹十三、母親に女優・宮本信子を持ち、更に祖父には日本映画の祖と呼ばれる偉大なる監督・伊丹万作…といった映画人の家系を持つ俳優・池内万作。彼を取り巻くこうした環境が、俳優を志す起因となる大きな部分を占めるかと思いきや、そこに対する返答は極めて淡白なものだった。「自分の両親の仕事が、たまたま俳優や監督だっただけです。親の仕事に影響を受ける人もいれば興味の無い人もいるでしょ?むしろ最初は後者だった気がします。」と言う通り、池内が演劇そのものに興味を示し始めたのは19〜22歳の頃だ。家を出たくて留学したという2度目の留学先(ロンドン)で演技を本格的に学び「そこで初めて舞台に立った時、あれっ?何か面白いと感じたんですよ」と当時を振り返る。「イギリスのコメディが好きだったので、将来は人を笑わせる役者になりたいな…と漠然と考え始めたあたりが役者を目指した最初でした。だから、特に役者になろう!と幼い時から考えていたわけではないのですが、それじゃあ、役者をもしやっていなかったら…と、今にして思えば想像がつかないので怖いものがありますよね」 その後、帰国した池内はアメリカとドイツの合作映画ハル・ハートリー監督が手掛けたオムニバス『FLIRT フラート 東京編』でデビュー。続く、渡邉孝好監督による戦争青春映画『君を忘れない』での演技が高く評価される。池内が扮したのは、出撃前の若き特攻隊員たちを描いた本作において、唯一妻子を持つ隊員の役だ。戦果報告のため一人突撃せずに無傷で帰還するように命じられた男の葛藤を見事に表現していた。まだデビュー2作目だというのにタイトルバックで6番目に名を連ね、堂々たる演技を披露していたのは記憶に新しい。まだ20代の池内が見せる“家族を想う感情”を押し殺した演技は、まるでベテラン俳優のようであった。中でも、どうして飛行機乗りになったのか?と仲間に尋ねられた時に「飛んでしまえば独りになれるから」と答えるシーンの演技と、ラスト近くで隊長より戦果確認のため特攻せずに帰還する事を命じられた時の取り乱す演技は、今観ても鳥肌が立つ思いだ。それから6年後、高橋伴明監督が、連合赤軍のリンチ殺人事件を描いた問題作『光の雨』で、彼の演技に、今度はゾクッとする得体の知れない何かを感じた。「革命を起こしたかった。皆が幸せに暮らせる世界を作りたかったんだ…」というナレーションで始まる本作。主人公の一人、リーダー格の青年を演じた池内万作のモノローグは無味乾燥として…それでいて一言一言に、自責の念に苛まれている苦痛のようなものを感じさせる。明らかにこの作品を境に彼の演技が変わったように思えるのは私だけだろうか。 コンスタントに様々な役を演じてきて「やっぱり、役者として色々な役が演じられないと面白くないし…作品を観た人から“池内万作はいつも池内万作だよね”って言われたくないですしね。」脚本をもらった時点で、“今回はこんな風に演じてみようかな”ってあれこれ考えるのが楽しいと語る池内。その結果、自分なりに反省と試行錯誤を繰り返しながら独自の演技を見つけ出してきているという。最近、印象に深く残るのが『犯人に告ぐ』で演じた主人公の刑事に100%の信頼を寄せつつ、かつて自分の失敗により主人公を閑職へと左遷させてしまった負い目を持っている人当たりの良い刑事。見事、クライマックスでは、彼が連続誘拐殺人犯を見つけ出すのだが、その際に自分が発見した驚きと疲労からヘタレ込んでしまう姿(極度の緊張感溢れる映画の中で快感と和みが同居するシーンだ)は池内にしか出来ない演技だと思った。前述の役者に興味を持った時の話で「人を笑わせる役者になりたい」と語っていたが、その思いが形となって現れていたシーンである。 今年に入って吉田松陰を描いた映画『獄(ひとや)に咲く花』、大河ドラマ『龍馬伝』と幕末を描いた作品が続くなど、コンスタントに活躍している池内万作。秋には妻夫木聡主演の『悪人』など話題作が目白押しだが、その中でも注目したいのは、8月7日からは池内万作主演による政治家や官僚、元軍人が、それぞれの立場で第2次世界大戦の体験を語る座談会を描いた『日本のいちばん長い夏』。7月31日には、NHK BS-hiにおいて放映されるといったクロスメディアによる公開が話題となっている。 |
|
|
Produced by funano mameo , Illusted by yamaguchi ai
copylight:(c)2006nihoneiga-gekijou |