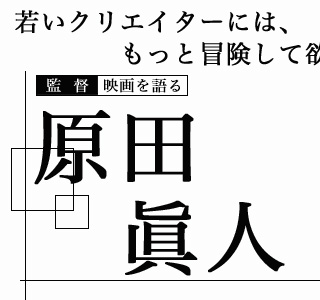|
 |
「映画と、それに関わる人間と、その時代を描くボグダノビッチの眼。それはフォードが、西部の人間たちや、自然を見つめた眼ーそうした自分の映画を作るためにスタッフやキャストと人間的にかかわり合った、愛情をこめた眼、にそのままつながるものであるように、私には思えるのだ。」これは、キネマ旬報1972年夏の特別号に掲載された映画『ラスト・ショー』における評論の一部を抜粋したものである。それを寄稿したのは、当時ロンドンに語学留学中だった若き日の原田眞人監督(誌面には真人と表記されていた)だ。意外な事に、後の『クライマーズ・ハイ』や『わが母の記』を手掛けた原田監督が映画業界に始めの一歩を踏み出したのは映画ジャーナリストとしてだった。映画監督・原田眞人を語る上で『ラスト・ショー』との出会いを欠かす事が出来ない。 ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2013のコンペティション部門で審査員を務めている原田監督に、現在の日本映画界を取り巻く課題から映画祭に期待する思いについて、自身の体験を元にお話を伺う機会に恵まれた筆者は、取材後、その足で原宿から神保町へ。閉店間際の矢口書店へ駆け込み、10分だけ延長をお願いしてお目当てのキネマ旬報を見つける。(おおっ、さすが天下の矢口書店)原田監督の書かれた『ラスト・ショー』論評は作品のレビューというよりもロンドンにあるナショナル・フィルム・シアター(以降N.F.T)で開催されたピーター・ボグダノビッチによる特別レクチャーで上映された長編処女作『ザ・ターゲッツ』を中心に紹介されており、ボグダノビッチ作家論といった内容だった。(その前のページが渡辺武信氏による完全な作品レビューだったので編集部からの要請があったのかは定かではないが…)原田監督の視点は、この頃からボグダノビッチやジョン・フォードなど監督に向けられていたのが興味深い。高校時代から映画監督になりたいという夢を抱いていた原田青年だったが、「監督になるにはどうすればよいか分からない。そもそも監督って何だ?と思っていて、それが解決したのが、この留学中の23歳の頃でしたね」と、当時を振り返る。「今はDVDで映画が観られるけど、当時は映画を観る環境が充実していたのはロンドンとパリが双璧だったんです」そもそも、原田青年が語学留学先をロンドンに選んだのは、N.F.Tに半年間通えば、色々映画を観る事が出来て、同時に英語も学べるから。ところが、その判断は正しかった。そこで映画の世界に入るキッカケとなる『ラスト・ショー』と出会う事になるのだから。そして、アメリカで初めて評論家から映画監督になったボグダノビッチの記事を、後に同じ道を歩むことになる原田監督が初めて書いたという偶然に、運命的なものを感じてしまった。 また、原田監督はN.F.Tで、もう一人の映画監督と運命的な出会いをする。それは『ラスト・ショー』の劇中で閉館される映画館が最後に上映する映画『赤い河』の監督ハワード・ホークスだった。「劇中で使用されていた『赤い河』の印象が、自分の記憶にあるものと違う…と感じたんです。ひょっとすると今『赤い河』を観ると別の観点から観られるのでは?」と思い、ホークスの研究を始める。「こんな映画監督になりたい」という明確なビジョンが生まれたのは、ちょうどN.F.Tで行われたホークスの特集上映の中で、1939年に製作された『コンドル』を観た時だったという。「ケイリー・グラント演じるリーダー格の主人公の姿に、きっとホークスのようなポジションなのだろうな…と感じたのです」いくつもの文献を読んで行く内に、ホークスに会いたいという思いが強くなった原田監督だが、意外と早くその思いは現実のものとなる。ある映画祭で行われた回顧週間に招かれたホークス監督に接見するチャンスが訪れたのだ。半年後、ロサンゼルスに移り、映画ジャーナリストとして活動する原田監督はパームスプリングスにあるホークスの自宅を訪ね、親交を深める。常々、ホークスから「とにかく脚本を書け。書いたら早く見せろ」と言われ続けて完成したのが、監督デビュー作でもある『さらば映画の友よ インディアンサマー』だった。 「ホークスが僕の師匠」と公言する原田監督だが、「その2年前にホークスは亡くなっていて脚本を見せられなかったのです。せっかくイイ機会に恵まれていたのに、それを活かせなかった事が悔しくてね。それまで書き溜めていたものをまとめて3ヶ月で書き上げたのがこの作品だったわけです」勿論、いきなり脚本を書いたからといって、すぐに映画が撮れるわけではない。原田監督の場合、既に映画ジャーナリストとして活動してる時に配給会社や製作会社とのパイプが出来上がっていたのだ。脚本執筆中から川谷拓三をイメージしていた原田監督は、知り合いの映画ジャーナリストのコネをつたって川谷拓三の快諾を得る。原田監督は「まぁ、ビギナーズラックみたいなもの」と、言われていたが、決してそんな事はない。留学先で評論を書いて、数々の映画祭に参加し、ジャーナリストとなった基盤があったからこそ。そこで生まれたつながりは明らかに原田監督の行動力の結果であり、ビギナーズラックとひと言で片付けてはならないのだ。 欧米の映画で育ってきて、自分に合ったテンポとは何なのか…を常に考え続ける原田監督作品の特徴と言えば、登場人物たちが繰り出すセリフの応酬と、その都度切り替わるアクティブなカメラワーク。例えば、『金融腐蝕列島・呪縛』で役所広司と椎名桔平が演じる若手社員が強制捜査の入った銀行を立て直すために議論する場面や、『クライマーズ・ハイ』で突然入電された共同通信によるジャンボ機墜落事故の一報でざわめき出す北関東新聞社内の光景。やがて、報道指針を巡る記者たち(最終的に販売や営業にまで広がる)の意地のぶつかり合いに発展する…原田監督は石上三登志との対談で、その様を「言葉のボクシング」と称していたが、観客が受ける印象は正にその通り。堤真一と堺雅人を主軸に据えて(原田監督曰くメーンイベント)そこに様々な思惑を抱いた人間たちがガンガンぶつかってくる。驚くのは、こうした骨太な社会派ドラマに限らず『わが母の記』のような文芸作品でも同様の印象を受けた事だ。冒頭、軒先で雨宿りする少年時代の主人公が母親と向かい合う豪雨のカットに続く、伊豆の実家に集まった兄妹たちがちゃぶ台を挟んで交わす家族の何気ない会話シーン。緩急自在に切り替わるカメラワークに、室内シーンであるにも関わらず、アクション映画のような興奮を覚える。こうした演出のテンポについて原田監督は、野球に置き換えて説明する。「ピッチャーがストレートばかり投げていたらいつか打たれてしまう。カーブやシュートと組み合わせるのと同様に、ロングレンズやワイドレンズを使ったショットを組み合わせているわけです。監督は映画を作る上で先発ピッチャーのメンタリティを持っていなきゃダメなんです。もちろん、カットを細かく刻んでしまうとカッタルイだけになっちゃいますけどね(笑)」例えば50人の編集スタッフから構成された『クライマーズ・ハイ』は、編集者の視点を変えるだけで何百通りの組み合わせが生まれる。その時にベストだと思ったところを取って行くのだと原田監督は語る。 |
|
|
Produced by funano mameo , Illusted by yamaguchi ai
copylight:(c)2006nihoneiga-gekijou |