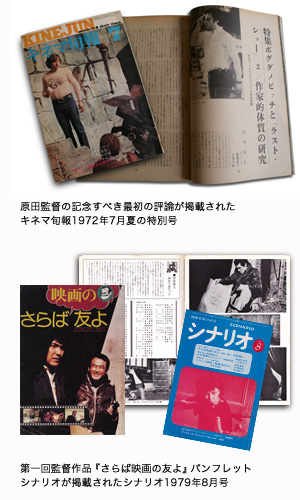|
 |
今回、審査員を務める原田監督は、若手が成長する場としてはショートショートフィルムフェスティバルに大きな期待を寄せている。「映画界の新陳代謝のためにも若手の発掘というのは重要な事。今年の応募作品の中にもスゴイと思う作品があって、これから長編の監督として成長していくだろうな…と思ったクリエイターが5〜6人いました。残念ながら日本人はいなかったけれど」と、厳しい意見を述べながら、若手クリエイターたちに「もっと古典の名作と呼ばれている作品を観て勉強した方が良い」と進言する。前述の通り、今もなお観続けられている名作には、名作と称される理由があるからなのだ。ただ、原田監督は古典を学ぶ環境においては海外に比べて日本は遅れているとも指摘する。「例えば海外のDVDに収録されている特典の情報量が半端ないんですよ。若者たちは、そういうのを日常観て勉強しているのだから、どんどん差が広がって行く。海外の優れた監督たちは古典(映画)をちゃんと勉強していますからね」そうした中で今年、グランプリに輝いたイギリス映画『人間の尊厳(原題:It was my city)』と、アジアインターナショナル部門で優秀賞を獲得したイラン映画『私の街(原題:It was my city)』は、原田監督の言葉通り突出したクオリティと強烈なメッセージを有していた。特に後者の『私の街』は、自国政府による厳しい検閲があるにも関わらず8分という短い時間で戦争批判した素晴らしい作品だった。 一方、日本は表現の自由が約束されていながらもリスキーな題材には出資者が集まらないという現実がある。例えば、実際にあった事件の映画化がそうだ。以前。原田監督は雑誌の取材で「それぞれのパートのプロが自分たちの技術を尽くして、語るべき理念を世界に提示できる最も効果的な手段が映画」だと述べていた。『突入せよ!『あさま山荘』事件』や『クライマーズ・ハイ』、『金融腐食列島 呪縛』で報道では見えない社会の一部を切り取ってきた原田監督は、今まで何度も制約という壁にぶつかってきたという。「勿論、若手にいきなりタブーに挑戦しろというのは無理な話だと思うけど、だからと言って自分の身近な事ばかり描いても仕方ない。ある程度のところまで来たら、社会性のある題材にも挑戦すべきだ」と、映画祭にエントリーされた日本の作品を振り返って語る。「最近の若い人たちからはタブーに挑戦しようという気力が感じられない。もしかするとタブーがある事すら意識していないんじゃないかな?とさえ思えるくらい自分の身の回りしか見ていない作品が多い」それを打ち破るために、一旦、海外に出て日本を見つめてみるのも良いだろうと原田監督はアドバイスする。「外では色々な人が、様々な問題を抱えている。そこで、日本はどうなのかと、見つめ直すという姿勢が必要だと思うのです」今、何がウケているのか?ばかりを追求する風潮の現在のクリエイターに対して「もっと冒険してほしい」と、原田監督は苦言を呈する。「これから裾野が広がっていけば、実力のある人材を発掘する場として、もっと注目される映画祭になるはずです」そうしたチャレンジの場として映画祭を活用する若きクリエイターにかける期待も大きい。 取材:平成25年6月2日(日)ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2013会場 ラフォーレミュージアム原宿にて
|
|
|
Produced by funano mameo , Illusted by yamaguchi ai
copylight:(c)2006nihoneiga-gekijou |