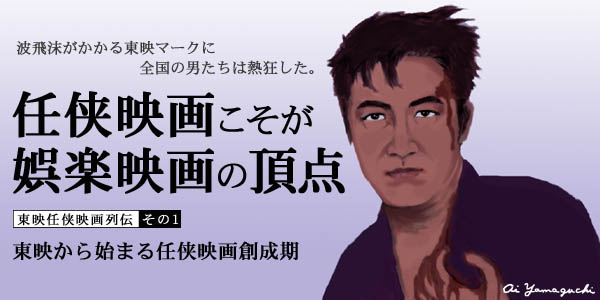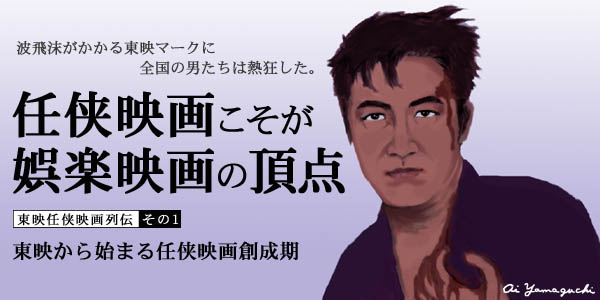

東映の任侠映画は鶴田浩二から始まり、高倉健で絶頂期に到達し、藤純子で終焉を迎えた…と、ある東映直営の映画館館主が口にしていた事を思い出す。昭和30年代、まだテレビが普及し始めたばかりで脅威に感じられていなかった頃…国内の映画館は毎年200館近く増えていた。ハリウッドを中心とした外国映画よりも日本映画の数が多かった時代だ。各映画館では土曜の夜にはオールナイト興行を行い、客席からは「健さん危ない!」といったかけ声が掛かるのは当たり前。大阪の劇場では映画館の中庭で、熱くなった若い衆が喧嘩を始めたというエピソードまで残っている。
そんな日本映画のピークに大きく貢献し、熱狂的なファンを確保していたのが“東映”任侠映画である。戦後間もない頃、GHQからの命令で時代劇や戦争映画は国内で製作は禁止されていた。敗戦直後の国民が愛国心と闘争心を高揚させる武士道の精神を善しとする映画を危険視したのは無理もない事だ。庶民は大衆文化のメインであった時代劇というジャンルを取り上げられ欲求不満に陥っていたのだが、それを打開したのが多良尾万内シリーズの探偵ギャングものだった。それまで時代劇スターとしてチョンマゲを結っていた俳優が帽子とコート姿でスクリーンに登場。悪人を銃で撃ちまくる姿は、刀で悪代官を切り捨てる姿の代わりとなった。講和条約締結後の昭和25年以降に、ようやく時代劇が解禁となったが、この期間に誕生したマフィアものと時代劇がミックスされた任侠ものが誕生したのは自然な流れだった気がする。鶴田浩二主演の『人生劇場 飛車角』から日本で任侠映画という新しいジャンルを生み出したのが“株式会社東映”であり、以来現在に至るまで東映という映画会社のカラーとして印象付けられる事となった。
鶴田浩二が東映でスターとなったのは紛れも無く「人生劇場飛車角」シリーズにおける着流しの渡世人、飛車角だ。爆発的な大ヒットとなり、翌年には続編「人生劇場続飛車角」が公開、さらには名作として名高い「博徒」が公開。ここで初めて、東映任侠映画を軌道に乗せた名プロデューサー、俊藤浩滋と最多の任侠映画を監督した小沢茂弘、そして鶴田浩二というトリオが顔を合わせたわけである。「人生劇場」で任侠映画の基盤を作り、真の意味での任侠映画の始まりは「博徒」と言われるだけあって、ヤクザ、渡世人の社会を正確に(?)描いた最初の映画である。今までに無かった男の世界を生き生きと演じた鶴田の姿に当時の観客は、クライマックスの殴り込みのシーンで大いに湧いたという。大阪では主婦たちが“ヤクザ映画反対”のデモを起こす等の社会現象まで引き起こしたのだ。
昭和30年代から40年代はその他の大手4社もこぞって任侠映画を作り出し各社独自のカラーを打ち出した作品を残している。が、任侠映画の顔となるべきスターを有している東映は事実上、任侠映画に関しては一人勝ち状態だったと言っても良いだろう。そして、こうした映画を作るノウハウを持った監督・スタッフが充実していた事も大きな要因だったと思われる。そんな監督の中でもマキノ雅弘監督は観客の喜ぶ娯楽映画を作らせたら右に出る者はいないと言われるだけあって、任侠映画の盛り上げ方は抜群であった。藤純子の引退記念映画「関東緋桜一家」を作ったマキノ監督はラストで藤純子にあたかも観客に向かって引退の挨拶をしているような…といった粋な計らいをしている。その作品を最後に東映は実録ヤクザものに移り変わっていく。

任侠映画だけではなく“男はつらいよ”シリーズでもよく見かける「仁義」を切る。「仁義」とは、任侠世界における初対面の挨拶として行う特定の儀礼様式(対外儀礼)のことを指している。「仁義」という言葉は、「辞宜」が転訛したという説と、「時宜」であるという説があると言われている。こうした「仁義」が博徒や的屋仲間などの社会で行われるようになったのは、遠く江戸時代にまでさかのぼるといわれ、「仁義」を行うことを「仁義をきる」といい習わしてきた。
この対外儀礼としての「仁義」には、「渡世人の七仁義」といわれる7種の「仁義」があるといわれており、1)伝達の仁義、2)大道の仁義、3)初対面の仁義、4)一宿一飯の仁義、5)楽旅の仁義、6)急ぎ旅(早や旅)の仁義、7)伊達別の仁義…である。これらの「仁義」を博徒仲間では、正式には「チカヅキ」(近づきの仁義)、的屋仲間では「メンツー」(面通)とか「アイツキ」(テキヤ用語、アイツキ仁義)といっていた。ただ、映画で正式な「仁義」のきり方を正確に描いている作品は少なく、限られた時間の中で5分近くも掛かる「仁義」を描写しては時間がかかり過ぎるというわけで略式の「仁義」で雰囲気だけを伝えている物が多い。(参考サイト:Webさんいん「暴力団追放協議会」)
その中で『昭和残侠伝』においては、池部良演じる渡世人が神津組の玄関口で正式な仁義をきるシーンを見る事ができる。「仁義」の口上では、面識のない相手方に対し、独特の言い廻しで先ず自己の姓名所属団体等を披瀝した上、用向きを述べるのが独自の礼儀作法というわけだ。それまで、任侠映画の出演を頑に拒んでいた池部だが、本作で見せてくれた仁義は、その筋の専門家に手ほどきを受けただけに任侠映画史上、最高の仁義シーンとなった。ところが、本人は長い時間(映画では3分という長い仁義)、中腰のまま仁義を切っていたため撮影終了後にはぎっくり腰となったという逸話が残されている。それだけ、迫真の演技だったわけだ。こうした旅から旅へと各地を転々とする渡世人が一宿一飯に預かる際、他にも礼儀というものがある。言わば他人様の家にお世話になるわけだから、この世界のマナーをわきまえていなくては、一人前の渡世人とは言えないのである。その作法を細かく描いていたのが『昭和残侠伝 吼えろ唐獅子』。夕食で出された膳を前にして、いきなり食すのではなく懐から一枚の上を取り出す。おかずが魚だった場合、骨などの残飯は一々紙の上に乗せて、食べ終わったらそれを丁寧に包んで持ち帰る。決してご厄介になっている一家に食べ残しを置いていかないのがマナーなのだ。また、ご飯のお替わりも中心だけを食べ、3分の1程度のところでお替わりをして早々に食べ終わる事も大切なのだ。そして、その一家で賭場が開かれていた場合、遊ぶのは良いとしても半の目の時に入るのではなく丁の目の時に入るものと、いうことも描かれている。任侠映画では綿密な取材の元に、こうしたルールが細かく紹介されているのでそれを観るだけでも楽しい。
最後に、『昭和残侠伝』の中で池部良が切った仁義を紹介しよう。「ご当家、軒下の仁義、失礼ですがおひかえくだすって」…その言葉に、相手がひかえると、本格的な仁義を切る。「早速ながらご当家三尺三寸借受けまして、稼業仁義をはっします。手前、旅中の者でござんす。是非とも御兄ぃさんからおひかえなすって。早速おひかえくだすってありがとうございます。手前粗忽者ゆえ、仁義前後を間違えましたる節は真っ平ご容赦願います。向かいまして御兄ぃさんには初のお目見えと心得ます。手前、小国は大日本帝国日光筑波党。関東は吹き下ろし、家集は宇都宮でござんす。稼業、縁持ちまして身の片親とはっしますは、家集、宇都宮に住まいを構えます十文字一家、三代目を継承致します坂本牛太郎に従います、若い者でござんす。姓は風間、名は十吉。稼業、昨今の駆け出し者でございます。以後万事万端宜しくお願いなんして、ざっくばらんにおたの申します」。