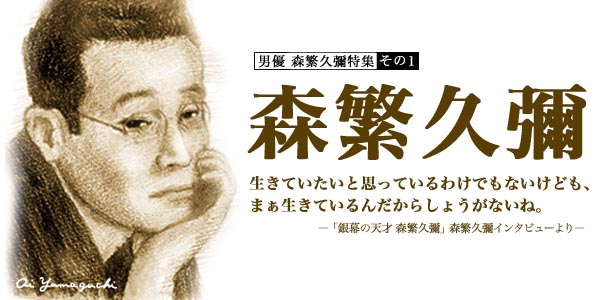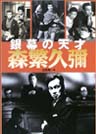|
|
そして、その翌年の昭和28年、森繁人気を決定付ける作品に出会う事になる。名匠・マキノ雅弘監督作『次郎長三国志』シリーズの森の石松役だ。(ここでは勿論、森繁のトレードマークであるチョビ髭は存在しない)全9作中7作に出演した森繁は回を追う毎に人気が高まり、道を歩いていても「石松!」と声をかけられる程のハマり役を獲得(ただ本人は役名で呼ばれるのをかなり嫌っていたらしいのだが…)したのだ。初登場となったシリーズ2作目『次郎長初旅』では終盤に森繁の石松が出てくる。ひどいどもりなのだが一端、啖呵を切ると流暢に喋り出す…たった数分の出演シーンであるにも関わらず、そこから映画の雰囲気は確実に変わってくる。続く3作目『次郎長と石松』では、タイトルが示す通り森繁石松が活躍する実に楽しい作品となる。石松最期の『東海一の暴れん坊』に至っては事実上、森繁単独の主演作であり、シリーズ最高の出来となった。敵に囲まれながらも「俺は死ねねぇんだよ」と笑みを携えながら斬られる“森繁の石松”は、最高にカッコ良かった。ちなみに、マキノ監督が日活で製作した『次郎長外伝 秋葉の火祭り』(東宝の『次郎長三国志』とは全くの別物である)でも、森の石松を演じている。昭和30年、森繁は遂に、彼の生涯における代表作を得る事となる。豊田四郎監督作『夫婦善哉』だ。本作は、芸術祭に参加して“文部大臣賞”を受賞する。この年から文芸作品が多くなる森繁…世間の見る目も明らかに変わってきたのもこの頃からだ。脇役の頃は、いかがわしさだけが際立ったペテン師のような役が多かったものの再びマキノ雅弘監督と組んだ名作『人生とんぼ返り』の“芸のためなら女房を泣かす”男の役を観ていると、脇役時代は決して無駄ではなかったと思う。そして、偶然にも『夫婦善哉』のクランクインの遅れから出演した久松静児監督『警察日記』で人情味溢れる田舎の警官を演じ大ヒットを記録。順調に『夫婦善哉』が撮影していたら、この名作は生まれなかったかも知れない。人情喜劇に限らず社会派のシリアスドラマ『神阪四郎の犯罪』や『森繁よ何処へ行く』が封切られる等、昭和30年代に発表されたこれらの作品によって、単なる喜劇俳優ではない事を世に知らしめた。 森繁は、後にマキノ監督と豊田監督について、こう語っている。「マキノ監督は、私の活動写真のお師匠さんです。この方から映画のコツを盗むだけ盗んだ」…『次郎長三国志 東海一の暴れん坊』のクライマックスでマキノ監督が的確な立ち回りの演出をつけて、それが見事に決まった事を感心していた。その立ち回りをつける殺陣(タテ)師を題材としたのが『人生とんぼ返り』。森繁は、この中で主人公・殺陣師・段平の役を演じる。次郎長シリーズで、さんざんマキノ監督の演出を見てきた森繁だからこそ、殺陣師の身のこなしを完璧に表現できたのだろう。そして、『夫婦善哉』で初めて顔を合わせた豊田四郎監督については、突然渋谷の料亭に呼び出されて「織田作之助の小説を映画化して映画界に新風を巻き起こしてやろう」と話を持ちかけられたのがキッカケでその後、駅前シリーズ等…数多くの作品でコンビを組む事となる。翌年、豊田監督とコンビを組んだ『猫と庄造と二人のをんな』も忘れられない名作のひとつ。飼い猫リリーを愛する男を中心に、母、先妻、後妻が繰り広げる谷崎潤一郎原作の愛憎喜劇だ。森繁の演技以上に、試写を観に来た谷崎が猫の演技を褒めていたという。しかし、その猫の演技を引き出したのは、紛れもない森繁の臨機応変な演技力があったからだというのは一目瞭然。機会があれば是非、この作品も取り上げたいと思う。以降、森繁は“駅前シリーズ”、“社長シリーズ”と2つのドル箱シリーズを有し東宝喜劇の看板スターとなるのだが、それは次回に紹介させていただく。
|
|
|
Produced by funano mameo , Illusted by yamaguchi ai
copylight:(c)2006nihoneiga-gekijou |