

平成9年12月20日、伊丹十三が死んだ…しかも飛び降り自殺だったとニュースで聞いた時、耳を疑った。自殺とは程遠いと思っていた人物の一人だっただけに、しばらくは何かの間違いでは…と現実を信じる事が出来なかった。丁度、バブルの前後13年間に製作した10本の映画を残して逝ってしまった伊丹監督。名匠・伊丹万作監督を父に持ち、映画俳優から突然51歳の年に『お葬式』で監督デビューは、一体何ゆえの事だったのだろうか?殆どの作品の配給収入が10億を超えるヒット作となり、日本映画を代表する監督にまでなったというのに…。一旦撮影が始まると食事をロクに摂らずに撮影に没頭していたという伊丹監督にとって映画は命を削って作り上げるものだったのだろうか、それにしても…である。
今一度、伊丹十三が監督した映画を観直してみると、ある種の傾向が見えてくる。処女作『お葬式』は、実際に自分が体験した“お葬式”(妻・宮本信子の父親が亡くなった時の葬儀がモチーフとなっている)の光景を客観的に見た時、こんなに可笑しいものなのか…と思い「これを映画にしない手はないぞ」と閃き、早速、映画化に向けた資金集めを始めたという。主演を務めた山崎務は『お葬式』について「僕は『お葬式』には伊丹十三のすべてがあると思う」と後に述べている(新潮社刊「伊丹十三の映画」より)が、正に第一作となるこの映画に伊丹監督は自身のエッセンスを全て投入していたと思う。はっきり言ってしまえば、この後に続く作品は、題材が異なるだけで基盤となるテクニックやプロセス、論じ方のギミック等は『お葬式』の焼き直し(言っておくが決して否定しているのではない)と言っても良いだろう。つまりは、映画監督が何年もかけて築き上げるものを伊丹監督は、第一作で既に確立してしまったのだ。だから一見違うように見える作品だが、しっかりと根底には伊丹十三自身が存在しており、観客は何となく「伊丹監督っぽい」と思いつつ観るのである。よく『お葬式』を小津安二郎監督の映画になぞらえて論ずる方がいるが、私はそうは思わない。多分、抑揚の無い淡々とした台詞回しや固定したカメラアングルがそう感じさせるのかも知れないが、これらの間やリズム…そして、時折垣間見える“毒っ気”や“喪失感”は間違いなく伊丹監督のオリジナルである。式が始まる直前に山崎務が愛人関係にある高瀬春奈と屋外で身体をむさぼるようなセックスシーンをあえて入れたのがイイ例だ。その後作った『静かな生活』(興行収入が振るわず失敗作と言われているがこれは伊丹監督最高傑作である)も『お葬式』と同じ伊丹流の時のリズムが存在していた。知的障害者に対するリアルな好奇の視線をカメラのファインダーにしてしまったのだ。
2作目の『タンポポ』は明らかに確信犯的に主軸となる物語にサブ的な小さな物語を交差させる…という変化球で描いてみせたが、時折見せるエロチシズムやシニカルな笑い等、伊丹監督のエッセンスが充分盛り込まれているのが認識できる。また、最大のヒットとなった『マルサの女』に珍しく爽快感を感じたと思ったら続編の『マルサの女2』は、毒っぽさが噴出。敵も味方も無く、果たしてマルサは勝利したのか?最後まで答えを見いだす事は出来なかった。三国連太郎の久しぶりに見せるワルぶりは惚れ惚れする程だったのに対して、本作のマルサの亮子ちゃんは明らかに後手に回っている。結局、勝利したのは権力を持つ政治家…というのも伊丹監督らしいシニカルな終わり方ではないか。次回作『あげまん』にしても一見ハッピーエンドなのだが主人公二人の関係は不安定であり、たにまちという政治や経済が陰で蠢く場所が舞台なだけにスッキリとした終わり方ではなかった。権力者をコケにするというのが伊丹映画の特徴となり、それに対して観客は怒ったり笑ったりするわけだ。『大病人』の宮本信子も癌に冒された夫である三国連太郎演じる映画監督に裏切られながらも最後まで看取る気丈な妻を好演。この役は『あげまん』と共通するところが多い。病室にまで愛人を連れ込む大監督ながら死を前にジタバタと弱さや脆さを浮き彫りにした点においてもバブル前夜の伊丹映画の特徴がよく現れていた。その点、『ミンボーの女』と『スーパーの女』は比較的ストレートに描いており、幅広い年齢層に向けて発信されていた。両作品共に一般市民とか消費者とか受け身の立場から見た問題を描いているから、変に毒っ気を混ぜてしまっては主題がぶれてしまうと考えたのかも知れない。両作品に共通するのは弱者が逆転する物語であるという事だ。どちらかと言えば、伊丹監督は権力が嫌いなようで、権力側から描いていた作品が意外と多い事に気付く。『ミンボーの女』では、暴力団員が伊丹監督を切りつけ重傷を負わせる事件が起こったが、伊丹監督は臆する事なく映画を公開させてしまい暴力に屈しないという主義主張を貫き通した。しばらく警察が身辺ガードをしてくれた経験から『マルタイの女』の構想を生み出したのだから大いしたものである。今では食品偽装が社会問題となっているが、その遥か以前にスーパーにおける日付改ざんを訴えていた『スーパーの女』は、かなり先見の明があったと言えよう。閑古鳥の鳴くスーパーを再生させる物語の中には、お客様を第一に考える事の大切さ…が大きなテーマとなっている。
遺作となった『マルタイの女』は正直言って従来の伊丹映画とは違う暗さがあった。確かに伊丹映画には、要所要所に毒っ気が存在していたのは確かだが、ここまであからさまなのは初めてだった。カルト教団の危険性を暴こうとしていた弁護士が信者に殺される現場に居合わせた女優が、裁判で証言するまでを描いた本作。本作では、それまでヒロイックな役を演じていた役者がこぞって正反対の役だった事に戸惑いも感じた。宮本信子は守る側かと思っていたら守られる側でしかもワガママな女優役というのだから、伊丹映画ファンが違和感を感じるのも仕方ないだろう。これまた常連の津川雅彦までが宮本信子を狙うカルト教団信者を撃った後に自分の額も撃ち抜いてしまうのだから(実は夢なのだが)。しかし、本作が最後になってしまったために、この先の伊丹十三が何をしようとしていたのかは分からず終いだが、確かに何かを変えようとしていた事は紛れもない。事実、本作の宮本信子の演技は、若干マンネリ化していた前作に比べて断然に素晴らしかった。特に、狂信的な信者に襲われる時のパニック演技は最高だ。10本目の節目に今まで築いてきたマンネリズムを破壊しようとしていたのかも知れない。だから、本作の撮影後に、今までの出演者が集まり皆で般若心経を読んだのではないだろうか?皮肉にも、これが伊丹監督の最後の会となってしまったのは偶然だと思う。
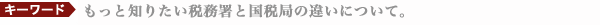
伊丹十三監督の3作目『マルサの女』と伊丹映画で唯一の続編『マルサの女2』で描かれている税金についてパンフレットで詳しく解説されているので、いくつか紹介しようと思う。まずは、最初に宮本信子演じる主人公が所属していた“税務署”と、マルサの異名を持つ“国税局査察部”の違いについて。基本的には、両者共に税金に関する業務を担っているのだが、決定的に違うのは、捜査に関する権限の違いが大きい。“税務署”の調査は「質問検査権」といって、調査に必要な書類等を当事者に出してもらう以外、強制的(勝手)に捜索したり差押えたりする事は出来ない。一方、“国税局査察部”の場合は、名乗りをあげて許可状を見せれば、社員の私物や着衣を調べる事も可能なのだ。言い換えれば、税金の警察と言っても良いだろう。『マルサの女』の冒頭に紹介されていたような、街の食料品店やパチンコ屋程度の脱税ならば“税務署”でも対応可能だが、組織ぐるみの巨額の脱税ともなると“国税局査察部”の登場となるわけだ。
では、“国税局査察部”=マルサの仕事とは何か?というと…まずは「目標の発見」だ。マルサは常に好況業種の企業をチェックしている。朝から晩まで新聞広告や雑誌をチェックしている部門もある程だ。また、これら情報収集の多くは“税務署”からで、各地域の“税務署”にはマルサの職員が常駐しており、パソコンの端末に入っているデータを自由に閲覧する事も可能だ。『マルサの女2』では、後輩の税務署員が任意の調査で目標となる宗教団体の施設に入るところをマルサである身分を偽って主人公が一緒に入り込むシーンがあるが、現実的にはこのような両者による合同捜索は行われていない。『マルサの女』で描いていたが、タレコミも重要な情報源。まぁ成功した人間には敵も多く、うっかり愛人と関係をこじらせて遺恨を残す別れ方をすると痛い目にあう事を肝に銘ぜよ。それらの疑惑が固まってくるといよいよ内偵が始まる。会社の経理状態や金の流れ等、ゴミを漁ったり雨の中張り込みをしたり、正に刑事のような捜査をするのだ。情報収集のためなら客になりすます…などは当たり前。『マルサの女2』で主人公の部下となったキャリアが対象者が経営するソープランドに客として入店して聞き込みをするシーンが登場する。長いものでは3年もの期間を内偵に費やす事もあるというが、そこで脱税の全体像が明確になったところで、ガサ入れとなる。ガサ入れとは、一斉立ち入り捜査の事で、作中で描かれていたがキーチェーンを切断するなどかなり強引な立ち入りを行う。勿論、当事者は外部と連絡をとる事は勿論、勝手に私物に手を触れてはならない。ここまでするからには、脱税が100%の確信がなければならない。警察さらながら、土足で踏み込んで何も無かった…では済まされないのだ。脱税を暴くには、売上除外、架空経費を焙り出して所得の詐称にたどり着く方法と、隠していた財産を見つけ出して結果から追求する方法の2通りがある。こうした調書は検察庁へ送られ、裁判となるのだが、有罪となれば最高懲役5年と脱税額に対して重加算税、本税、地方税、罰金を払う事になり、殆ど脱税した金額を持っていかれる事になる。だから、脱税は苦労した割にはリスクが大きいのだ。日本の行政を舐めてはいけない。下手するとどんなヤクザの取り立てよりも恐ろしいのだ。

伊丹 十三(いたみ じゅうぞう) JUZO ITAMI 本名:池内 岳彦
1933年5月15日-1997年12月20日没 京都市右京区鳴滝泉谷町。
名匠・伊丹万作監督を父に持つ映画監督、俳優、エッセイスト、商業デザイナー、イラストレーター、CM作家、ドキュメンタリー映像作家というマルチな顔を持っている。女優の宮本信子は妻、俳優の池内万作は息子、作家の大江健三郎は義弟である。
第二次世界大戦末期、京都師範付属国民学校(現・京都教育大学附属小学校)を経て、湯川秀樹によって当時構想された、科学者養成のための英才集団特別科学学級で教育を受けた。中学生の時に父・伊丹万作が死去。その後、京都府立第一中学校(現・京都府立洛北高等学校)から愛媛県松山市へ移り、愛媛県立松山東高等学校に転入し、大江健三郎と知り合う。卒業後、新東宝編集部を経て商業デザイナーとなる。
舞台芸術学院に学び、26歳の時大映に入社、「伊丹 一三」芸名を永田雅一にもらい俳優となる。1960年に日本映画界の巨人である川喜多長政・川喜多かしこの娘の川喜多和子と最初の結婚をする(1966年10月26日、協議離婚)。1961年、大映を退社後『北京の55日』『ロード・ジム』などの外国映画に出演し、話題となる。1969年に「伊丹 十三」と改名し、映画とテレビドラマで存在感のある脇役として活躍した。『家族ゲーム』、『細雪』では、キネマ旬報賞助演男優賞を受賞している。1960年代には、外国映画に出演した際のロケ道中をまとめたエッセイ『ヨーロッパ退屈日記』を出版しヒット。その後も『女たちよ!』など軽妙なエッセイを次々と発表し、文筆業にも活動の場を広げた。1970年代に入るとテレビ番組制作会社テレビマンユニオンに参加し、『遠くへ行きたい』等のドキュメンタリー番組の制作に関わり、この時培ったドキュメンタリー的手法は、その後の映画制作にも反映している。1970年代後半には『アフタヌーンショー』のレポーターを務め、“緻密な画力”で犯罪現場を生放送のスタジオで描いてみせた。1969年に山口瞳の媒酌で女優の宮本信子と再婚。
1984年、51歳で、『お葬式』で映画監督としてデビューし、日本国内で高い評価をうける。この作品で受賞した映画賞は、日本アカデミー賞を始めとして30を超えた。その後も『タンポポ』『マルサの女』『ミンボーの女』など、日本の社会に対する強い問題意識を掲げた作品で、日本を代表する映画監督となり、“伊丹映画”というブランドを築く事に成功する。1992年、『ミンボーの女』公開1週間後の5月22日夜に、自宅の近くで刃物を持った5人組に襲撃され、顔や両腕などに全治三ヶ月の重傷を負うが、「私はくじけない。映画で自由をつらぬく。」と宣言。警察は現場の車より山口組系後藤組の犯行であることを突き止めた。5人の組員が4年から6年の懲役刑となった。1997年12月20日、写真週刊誌「フラッシュ」により不倫疑惑が取り沙汰されたことに対して「死をもって潔白を証明する」とのワープロ打ちの遺書を残し、伊丹プロダクションのある東京麻布のマンションから投身自殺を遂げた。(Wikipediaより一部抜粋)
 |
 |
【参考文献】
伊丹十三の映画
271頁 20.6 x 15cm 新潮社
「考える人」編集部【編集】
2,100円(税込)
|

