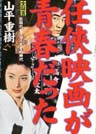以前、キネマ旬報別冊号で評論家の渡辺武信氏がやくざ映画を西部劇に例えていた。西部劇と一口に言ってもガンマン物、騎兵隊物、マカロニウエスタンのような残虐性を帯びた作品…と、実に幅広く曖昧なカテゴリに分かれており、やくざ映画はそれに似ていると、いうわけだ。戦前に作られた日本映画の父として有名なマキノ省三監督による『国定忠治』、伊藤大輔監督の『忠治旅日記』などは、当時としては、ひと昔前の世俗を描いたやくざ映画と言えよう。時代が江戸時代というだけで、描かれている人間は渡世人であり、親を泣かせる世界にどっぷり浸かっている事を後悔しているところは、同じである。昭和25年以降、GHQの規制が解かれ時代劇が解禁となってから、前述した2作品を含むマキノ雅弘監督『次郎長三国志』や加藤泰監督『瞼の母』といった股旅ものが量産される。時代劇に登場する侍とは違ったヤクザ者を主人公としたジャンルが確立され、任侠映画の前身となった。前述した西部劇の流れ者のガンマンが街の人々を救うべく、非業の限りを尽くす悪徳ガンマン共に立ち向かうのと同じ構成だ。例えば、“シェーン”のような流れ者が助けるパターンは『日本侠客伝』、“黄色いリボン”のような騎兵隊の群像劇は『昭和残侠伝』や『侠客列伝』のようなオールスターキャスト作品、“カラミティ・ジェーン”のような女性ガンマンが活躍するのは、さしずめ『緋牡丹博徒』といったところだろうか。
昭和30年後半に、東映任侠映画の第一弾『人生劇場飛車角』が公開され、いよいよ本格的な東映やくざ路線がスタート。時代劇とは違う、もう少し身近な現代劇…明治・大正・昭和初期を舞台とした任侠映画は庶民の中から生まれて来たヒーロー的な存在感を持って描かれる。映画の中で描かれるやくざは、常に弱者側であり、そこには人情劇がきっちりと描かれているのが受け入れられた要因ではないかと思われる。任侠映画におけるやくざは社会からはみ出した半端者…で、あるからこそ戦後の混乱した日本人が待ち望んでいたヒーローとオーバーラップさせていたのではないだろうか。昭和30年前半、日活が赤木圭一郎主演でシリーズ化していた無国籍アクションも彼の死によって終息を迎え、ちょうどそれと入れ替わるようにして登場したのが任侠映画であったのは、単なる偶然とは思えない。
昭和40年代に入ってから、東映任侠映画は高倉健というスターを主役の座に押し上げた事で日本映画における確固たる地位を獲得する。まさに昭和40年という年は任侠映画のエポックメイキングの年であり、看板シリーズが続々と登場する。ある映画評論家が「日本映画界の衰退を招いたのは東映任侠映画が原因である」と雑誌で述べていたが、それだけ東映の勢い(=量産体制とでもいおうか)は凄まじかったのだ。この頃から、任侠映画のマンネリ化が囁かれ始めるが、逆に東映ヤクザ映画ファンにとって、このマンネリが大事であって健さんと池部良が毎回肩を並べて悪党一家に殴り込みをかけるのを分った上で、その展開を求めている。実は、ファンは次に何が起こるか?誰が殺されるか?ラストはどうなるのか?なんて新聞広告で出演者の名前を見た時から先刻ご承知なのである。こうした定番の任侠映画で、高倉健のシリーズに一石を投じるかのように誕生したのが藤純子という任侠映画のヒロイン…それまで男社会であった任侠映画に女性が主人公の映画(マキノ雅弘監督は、それをキワモノ映画として最後までメガホンを取ろうとしなかった)『緋牡丹博徒』シリーズにおける緋牡丹のお竜である。これによって更なる勢いを増した東映任侠映画は、ここに最盛期を迎えたわけだ。10年間で約400本近くの任侠映画を作り上げた東映のような例は、日本は勿論、世界の映画史上類を見ないものであることは数字をみても理解出来るだろう。藤純子の引退と共に終焉を迎えた任侠映画は菅原文太を主役に迎えた『仁義なき戦い』を代表とする実録路線で再び息を吹き返し、プログラムピクチャー自体が消えるまで続いていったのである。
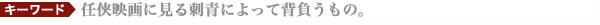
人の肌に直接墨を入れる「刺青」は任侠映画のシンボリックなカッコ良さと同時に、艶やかさという一面も兼ね備えている。「刺青」の題材は日活がよくロマンポルノのツールとしても使用しており、谷ナオミが墨を打たれて苦悶の表情を見せる下りは大きな見せ場であった。任侠映画ではクライマックスで相手の刃が着物を切り裂き、その間から見え隠れする「刺青」が物語の見せ場となっている。また、『緋牡丹博徒』といった賭博場を舞台として渡り歩いている主人公の場合はサイコロを振る時が勝負としての見せ場となっており、肩の刺青を披露する。遠山の金さん同様、任侠映画で「刺青」を見せるシーンはクライマックスと思って良いだろう。
「いれずみ」を「刺青」という文字をあてて呼ぶようになったのは、明治の末頃からで肌に刺した墨が青く見えるところから、「刺青」の文字をあてて呼ぶようになったといわれている。江戸初期に京阪神地方のいわゆる遊里において、男女間の心中立として、親指の付根と手の甲の中間に墨を刺すことが流行し、それを「入ぼくろ」と呼んでいた。それから次第に腕、肩、背中等に文字を彫るようになり、宝歴年間(1751年頃)になって全身に絵画的なものが彫られるようになったといわれており、その頃、専門の彫り師も登場した。この頃の「刺青」は「文身(ぶんしん〜文は模様の意)」あるいは、「ほりもの」と呼ばれ、遊里、鳶職、大工、佐官等の職人や商人などの間で、さらには、博徒、的屋などのやくざの世界で盛んに行われるようになったと言われている。「刺青」の絵柄も、牡丹(ぼたん)、唐獅子(からじし)、般若(はんにゃ)、金太郎、花和尚、地雷也(じらいや)、不動明王など、精巧なものが彫られるようになった。
『緋牡丹博徒 一宿一飯』でお竜が、悪玉に陵辱されてしまった娘に対し、いきなり片肌を脱ぎ自分の緋牡丹の刺青を見せて「自分は女だてらに、こぎゃんもんば背負って生きとっとよ…女と生まれて人を好きになった時、一番苦しむのはこの汚してしもうた肌ですけんね。消せんとよ、もう一生…だけん、体じゃなかつよ。人を好きになるのは心…。肌に墨は打てても、心には誰も墨を打つことは出来んとです」と切々と語るシーンはカッコ良いだけではない「刺青」を背負う事による悲しみを表現した素晴らしいシーンがあった。ちなみに、この作品で共演しているもう一人の女博徒を演じた白木まりの「刺青」は凛々しくも美しい弁天小僧だったのが印象に残る。
刺青のエピソードで、ユニークなのは昭和42年の『博奕打ち 一匹竜』の時…。主人公の鶴田浩二は、元博徒の刺青師で日本一の彫り師を決める刺青大会がメインの内容だったため、クライマックスで本物の刺青をした男たちが並ぶ壮観なシーンがあった。こうした撮影は他にも類がなく刺青保存会のメンバーに参加してもらって実現したのだが…。その中に、逮捕状が出ている人がいたらしく、運悪く任侠映画ファンの刑事が本作を観ている時に気がつき、あえなく御用になってしまったという。勿論、作品の中にはそのシーンは残っている。
また、映画のタイトル以上に有名になった『昭和残侠伝』の高倉健演じる花田秀次郎が背負う、唐獅子牡丹。プロデューサーの俊藤浩滋は、主人公が刺青を背負っている点で、映画の特徴が表れていると語っている。片肌を脱いだら唐獅子牡丹の刺青が現れる。観客席から「待ってました!」の声が一斉に掛かる瞬間だ。多分、本作から唐獅子牡丹という刺青はますますメジャーとなり、ヤクザ者の代名詞となっているように思われる。実は、本作のように金色や青色が入っている刺青は無いらしく(殆どが朱と黒らしい)この鮮やかな刺青が健さんの怒りが頂点に達すると同時にスクリーンいっぱいに映し出されるのだからファンにとってはたまらない。
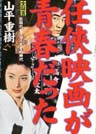 |
 |
【参考文献】
任侠映画が青春だった
284頁 21× 15cm(A5)徳間書店
山平 重樹【著】
|